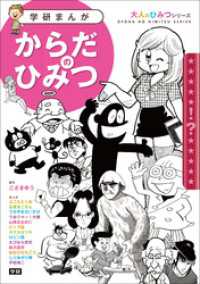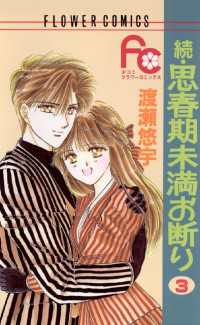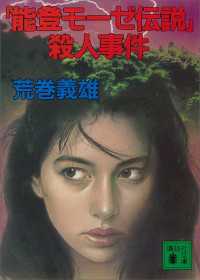内容説明
『枕草子』は、平安時代宮中に仕えた女房、清少納言が書いた随筆である。日本の古典の中で「徒然草」とならんで最もすぐれた随筆文学とされている。1000年の時を経てなお読みつがれる魅力、それは人間の心を深く見すえる目と、四季や風物に対するたぐいまれな感受性にほかならない。
目次
第1段 四季の美しさ―春はあけぼの
第8段 中宮がお産のために―大進生昌が家に
第9段 命婦のおとどという名のねこ―うえにさぶらう御ねこは
第23段 清涼殿のはなやかさ―清涼殿の丑寅のすみの
第24段 女の生き方―おいさきなく
第25段 興ざめなものは―すさまじきもの
第28段 いやな、にくらしいもの―にくきもの
第29段 どきどきするもの―こころときめきするもの
第30段 過ぎた日の恋しくなつかしいもの―すぎにしかた恋しきもの
第36段 七月のある朝のこと―七月ばかりいみじうあつければ〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kagetrasama-aoi(葵・橘)
34
日本語って清少納言の頃も現在も美しい!好きな段の一つ、第二三二段。月の明るい夜、牛車で川をわたると、水のしぶきが水晶のわれたようにくだけちってかがやく。まざまざと眼前に景色が浮かぶ文章。孫と一緒に読みたい一冊。2021/08/25
fu
19
あらためて読むと、初読みした子ども時代とは違う側面に気付かされる。そもそも人に見せる為に書いたのではなく、本音で思うがまま書き溜めていたにも関わらず心ならずも世に出た作品、と清少納言本人が言うように、胸中に秘めておきたいようなことも率直に綴られている。現代の一般庶民とは異なる社会概念や尺度、文化が垣間見える。 2015/12/14
花林糖
17
(図書館本)面白いのだろうけど大庭さんの訳が合わないのか、何度か挫折しそうになりながら読了。各段最後にある大庭さんの感想も省いてほしかった。このシリーズ好きなんだけれど残念。 2017/04/05
スズコ(梵我一如、一なる生命)
13
春はあけぼの、、、くらいしか知らなくて、でもその素晴らしさに憧れていました。また、このシリーズの源氏物語も素晴らしかったので、期待大でしたが、今回は外れました。原文の流れるような美しさが現代語訳で失われたからか、作品そのものよりもそこに流れる宮廷文化への憧れ加算が作品の評価を高くしていて、権力への俗物さなど本来自分が辟易するものはそのままそこにあってより醜く感じたからか、清少納言への苦手意識も強くなった。単に大庭みな子さんが合わないのかな、、、、。別のものをチャレンジしてみたい。2025/06/13
頼ちゃん
4
久しぶり。とりあえず訳で。華やかな宮中の描写の段にも、実は定子が不遇になっていた時期に書かれている段があることに気づいた。しかしその様子はなくて華やかで定子は美しく魅力的。清少納言はわざとそう書いたのだな。原文でも読もう。2024/08/02