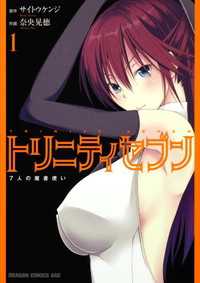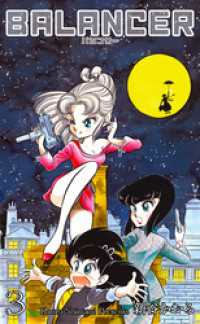内容説明
近代国家への歩みを始めた日本に国民国家の理念をもたらしたものは、上からの法制度や統治機構ではなく、大衆の側の浪花節芸人が語る物語と、彼らのメロディアスな<声>だった。前時代の封建的秩序を破壊し、天皇制の精神的支柱となった義理人情のモラルをつまびらかに分析、声を媒介に政治と芸能とを架橋して日本近代の成立を探る、斬新な試み。(講談社学術文庫)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
T. Tokunaga
1
読み始めて数十ページで気づいた。この話は現代日本にまったく通ずる。というのも、これは、尼崎の工業高校を出た某という漫才師の話とかなり近いのだ。いまや赤穂浪士とお軽勘平は、M1グランプリに駆逐されつつあるが、それがいやな感じを催すというと、それこそいやな感じがするひとが過半だろう。つまりそういうことである。2023/07/03
ちあき
1
浪花節という芸能のなりたちを追いながら日本における近代の成立を考察する本。芸能と政治を架橋する論考としてはおもしろかったが、〈声〉についての考察は物足りなさが残った(たとえば、教室で教科書を群読するという体験、ラジオ番組に耳を傾けるという体験との関連性など)。講談と浪花節の比較対照は説得力があっただけに残念。あと、「国民」および「国家」をある種のフィクションとして把握する思考に慣れていない人、浪花節そのものに関する知識が皆無の人にはハードルの高い記述もめだった。2009/11/06
1.3manen
0
浪花節の母体がチョボクレ・チョンガレ(35ページ~)。貧民街から出てきた芸能ということや、地方地方で言い方が青森の「ぢょんがら」などいろいろあり、面白いと思った(43ページ)。福澤諭吉の演説(53ページ~)も徐々に広まるものの、警察権力が介入する場面もあったようだ。「富貴の紊乱という表向きの理由とはべつに、民権派壮士の辻講談を取り締まるというねらいがあった」(107ページ)。思うに、言論弾圧、経済困窮となれば、庶民の生きる楽しみが必要だったわけで、今日の演歌にもぢょんがらが付く歌曲があるのも頷ける。2012/08/07
kungyangyi
0
浪花節から、下からの国民国家形成を見るという意図で書かれた本。浪花節師の歴史的具体的な記述が続いた後で、民衆芸能が想像の共同体を作り上げたと主張されるが、民衆と国家との関係や絡み合いについての記述が少ないように思える。ふたつがうまくつながって描かれていない。2021/06/17