内容説明
「中村屋ァ~!」「まってました!」。歌舞伎で芝居の途中に役者に向かって掛けられる絶妙な「掛声(かけごえ)」は、「大向う(おおむこう)」と呼ばれる歌舞伎通の人たちによるもの。学生時代に「大向うの会」に入会し、現在に至るまで活動歴56年の著者・山川静夫が、青春時代、そして大向う、昭和の名優たちとの温かい交流を描きます。
目次
第1章 わが青春の大向う
第2章 大向うの成立
第3章 大向うの人々と名優たち
第4章 大向う名人・水谷謙介
第5章 さようなら、こびき町!
現在活躍している歌舞伎役者の屋号
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
メタボン
27
☆☆☆☆ 北海道に住む私にはなかなか歌舞伎に触れる機会はないものの、この書からは歌舞伎の臨場感を感じられて良かった。初めて歌舞伎を見た時の団十郎の姿が目に焼き付いている。そして、大向こうからの掛け声も脳内再生されるのだ。舞台と観客の一体感を演出する「大向こう」の人たちは何とも粋なものである。2016/01/22
tom
15
2か月に1回くらいの頻度で歌舞伎を見てます。役者に「○○屋」などと声が飛ばす人がいるけれど、これが「大向こう」。山川静夫は、大学生の時代から、これを楽しんでいた。その彼が、歌舞伎のなれそめから現在までを語った本。大向こうをする人たちは、ずいぶんきちんと歌舞伎を見て、回数もこなして技術を磨いていたのだ。これには驚いた。残念なことに、私は、絶妙の「大向こう」を聞いたことがない。下手な芝居を見せられて、高い入場料を払ってることに腹が立ち、「よっ、学芸会」と叫びたくなることはあるのですけどね。2015/03/12
Yoshihiro Yamamoto
4
C+ ここ数年、月に2〜3回歌舞伎を観に行っているが、良い場面に接すると、役者に声を掛けたい衝動に駆られるようになってきた。しかし、この本を読んでみて、そんなことをするのは「10年早い」と思い知らせれた。そもそも、1階席から声を掛けるのはマナー違反であることすら知らなかったのだから…。また、「大向こう」と呼ばれる人々は声友会、弥生会、寿会のいずれかの団体に属しており、彼らは木戸御免とのこと。声を掛けるタイミングも、下座音楽や義太夫を理解して「間」を見つけなければならないとのこと。一本調子でもダメだそうだ。2014/12/21
きみー
3
歌舞伎の面白いところは、舞台の上で完結しない演劇なところ。舞台から一番遠い、幕見席、3階席からの大向こうはいつ行ってもいいものだなぁと感じていました。本作は全て昭和の歌舞伎座のお話です。昭和の名優と大向こうのやり取り、あたたかい交流が描かれています。歌舞伎の人を惹きつけてやまない魅力の1つに間違いなく大向こうの掛け声があるのでしょう。2016/10/23
つばな
3
昔の大向うはかなり自由度が高かったんだなあと思った。いまこんな面白い声を掛けたら針の筵な気がする。江戸っ子っぽい気風が、どうも上方育ちの私にはなじまない部分もありましたが、ともかく楽しそうでうらやましい。2013/07/10
-
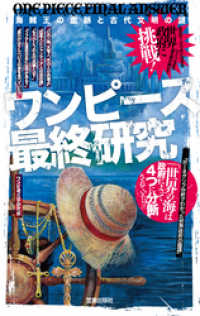
- 電子書籍
- ワンピース最終研究 海賊王の血脈と古代…




