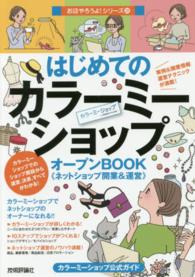内容説明
わたしはボートピープルだった――。サイゴンに生まれ、七回の亡命失敗の後に合法難民として日本に移住。その後、言葉の壁や経済的苦境を乗り越えて医師となった著者の目に、日本はどう映っているのか。蛇口をひねれば水が出てくる、親子が一緒に暮らせる、健康保険が存在している……日本には私たちが気づいていない数多くの幸福がある。波乱に満ちた人生を送ってきた著者が日本を見つめる、優しくそして鋭い眼差し。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月讀命
51
ベトナムで生まれ、ボートピープルの生活を続け、七回に及ぶ亡命失敗の末に、漸くやっとの思いで合法難民として日本に移住することが出来た著者は言う。言葉の壁や文化の違いを克服し、波乱に満ちた日々を送りながら、更には経済的苦境を乗り越えて医師にまでなった著者の目から見る日本の姿を描き上げる。日本人が、日本に住んでいて当たり前と思える生活が、実は世界的にグローバルな視点から見ると、幸福で尊いハイソサイティな生活であったりする事が伺える。人間、一度、インドやアフリカ等の未開の地に行くと感性が変わって成長するらしいが。2012/05/10
どんぐり
27
1978‐1981年(13歳~16歳の間)に、ベトナムからボートピープルとして7回の脱出を試みた竹永賢氏。その試みはすべて失敗に終わった。そして彼は、1982年にサイゴンから合法難民として日本に移住し、医師となった。この日本にいて、ベトナム時代のこと、家族のことを語りながら日本という異国で感じてきた幸福を素直に表現している。それは日本人にあってはなかなか気づかないことだった。17歳で初めて日本語教育を受け、日本の医学部に入って医師になったということも凄い。2013/12/05
スー
11
七回も亡命に失敗しても諦めず、日本に合法難民としてやって来て、言葉も通じないのに勉強を頑張り大学に入学し医師になった筆者に頭が下がります。サイゴン陥落後の生活や脱出時の苦労話は、あまり語られずに日本に来てからの話がメインでした。そっちの方が知りたかったのですが。しかし、日本での生活で水を贅沢に使える事にベトナム時代を思い出しながら、いかに恵まれているかを語られています。日本に生まれる事が幸運だと再確認し、感謝の気持ちを持つことの大切さを教えられました。2017/02/22
nchiba
9
ベトナムから難民として日本にやってきて今はお医者さんの著者の回顧録って感じかな。各国に散らばる家族の事を読むと、日本人は内に篭りすぎだなあと思った。もちろん著者は好んで故国をでたわけではないんだけど。いずれにしても日本人は幸福に慣れすぎているんだなあと痛感。読みやすい良い本です。2010/11/28
だいごろ
7
ベトナムから亡命してきて、日本人となった著者の視点で、日本の政治や社会について述べている。タイトルとは関係無いが、彼の兄弟で一番苦労した姉の言葉が印象に残った。家族の誰より厳しい生活を強いられた姉に対して、自分の運命を呪った事はないかを作者が尋ねた事に対する言葉。「一つのカボチャの木からできる実を見ればわかるでしょう。すべての実が形も、色も、成長する速度も異なる。同じであることを要求すること自体が自然の摂理を理解していない証拠なのよ。」2009/11/01
-
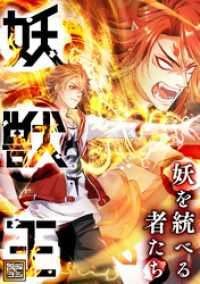
- 電子書籍
- 妖獣王~妖を統べる者たち【タテヨミ】(…