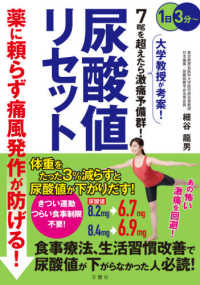内容説明
日本では森林という莫大な資源が増え続けている。多額の公共事業や補助事業が行われながら、建築材を採るために植林した人工林は切られず、木材自給率は二割である。林業は旧態依然とし、死傷事故も多発している。国産材と共にあった伝統木造は建築基準法で建築困難になった。我が国土で一体何が起こっているのか。リアルな実態を現場の「生の声」で伝える。森と木をめぐる社会の仕組みを根本から問い直す一冊。
目次
第1章 日本の森でいま、何が起こっているのか
第2章 日本の木を使わなくなった日本人
第3章 補助金制度に縛られる日本の林業
第4章 公共財としての森と欧州の発想
第5章 建築基準法で建築困難に陥った伝統木造
第6章 大工棟梁たちは何を考えているのか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あすなろ@no book, no life.
85
最近仕事上で知識得たく、山林の基礎本を図書館で借り出し読んでいる。その内の一冊。本書は大枠として森林事情・行政変遷・木造建築と分けられ、そこにフィールドワークや世界事例、加えて著者の些か多めの批判が加わる構成。しかし、その批判も含め知らぬ多量な知識は得られた。森の木材は消費して循環する。実は我が国では消費量を充分に賄える。これは、我が国に眠る膨大なる資源であると説く。何しろ国土の66%は森林なのだから。しかし、外材に頼る。長良川流域調査では、木造住宅の国産材使用量は3割を切る。2022/11/27
さきん
20
日本では森林という莫大な資源が増え続けている。多額の公共事業や補助事業が行われながら、建築材を採るために植林した人工林は切られず、木材自給率は二割である。林業は旧態依然とし、死傷事故も多発している。国産材と共にあった伝統木造は建築基準法で建築困難になった。我が国土で一体何が起こっているのか。リアルな実態を現場の「生の声」で伝える。森と木をめぐる社会の仕組みを根本から問い直す一冊。土地問題がなかなか痛い。2015/09/02
香菜子(かなこ・Kanako)
10
森林の崩壊。白井裕子先生の著書。日本の森林行政や森林管理の問題点がよくわかります。現行の森林行政や森林管理は無駄が多くて旧態依然。誰のための森林行政や森林管理なのでしょうと思いました。2018/01/18
桃の種
5
日本の林業も木のようにしなやかに。2020/02/05
かきたにたくま
5
需要と共有を無視した政策に増え続ける規制と、副題のとおり「国土をめぐる負の連鎖」がどのようなものかが分かりました。大きな方針の無いままその場しのぎを繰り返した結果がこうなんでしょう。2014/10/11