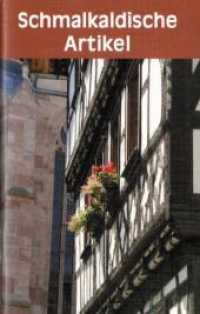- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
平成元年、週刊誌が坂本弁護士事件を報道して糾弾を開始しオウム真理教はにわかに注目を集める。その後オウムは一連の騒動を起こし、その間、幸福の科学も台頭、宗教は社会の重大な関心事となり、ついに平成7年、地下鉄サリン事件を迎える。一方、平成5年、万年野党だった公明党が連立政権に参加、11年以後、与党として君臨し、ついに日本は新宗教団体が政治権力を行使する国となった――。オウム、創価学会以外にもさまざまな新宗教やスピリチュアル・ブームに沸いた現代日本人の宗教観をあぶり出す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ntahima
34
新宗教、新々宗教を切り口にした平成20年史の筈が、一読感じたのが平成奇っ怪事件簿。ドイツ駐在を終えて帰国したのが平成元年であり、韓国に来たのが平成19年だから、私の知る日本の世相と内容がほぼ重なり、とても懐かしく読んだ。日本は仏教を除き外来宗教を殆ど受け入れておらず、キリスト教徒が1%にも満たない国は世界的にも珍しいらしい。某宗教がもはや民族化しているとの指摘には「上手い!」と思わず膝を打つ。最後に一言。気持ちは分るがオウム真理教騒動を巡る筆者へのパッシングに関する弁解、恨み節は別の本でやってほしかった。2012/03/01
小鈴
11
幻冬舎新書では平成20年に20年史ものを発刊したのだが、その宗教編。平成20年史はバブル経済を抜きに語ることはできないが、宗教も勿論影響を受けており、オウムがサリン製造装置開発する財力を手に入れたのはバブルによる余剰資金が寄進を通してマネー流入したからで。様々な宗教事件を20年というくくりで一気に読むといろいろ気づかされることが多い。いま宗教はどこに向かうのか。民族化する創価学会とおひとりさま宗教(真如苑)が、今の日本社会を現しているなぁと感じるのであった。 2011/04/25
荒野の狼
9
昭和63年(1988年)から平成20年(2008年)までにあった宗教関係の社会事件が各年10ページほどで簡潔に書かれており、1日あれば通読できます。各宗教の教義の理解のためではなく、宗教が社会に及ぼした影響の理解のための内容が中心です。単なる事件の羅列にとどまらず、著者自身の、これらの事件が引き金となったともいえる体験(辞職や病気)が織り込まれ、ドラマチックな内容になっています。2009/02/24
KJ
7
歴史を語る上で、政治を縦糸に経済を横糸にするならば、宗教とはその隙間を浸す水。宗教という視点から見ることで改めてその時代を面として捉える事が出来る。結局人は心の拠り所を求める。国家、地域、家族…そういった共同体が退潮すれば、その代替として宗教が台頭してくる。ただ無宗教を自認する日本人は、宗教との上手な付き合い方が不得手なのだろう。「信仰」に対する免疫がない分、内にいる者は時に暴走し、外にいる者は興味本位で騒ぎ立てることしか出来ない。「いかがわしい」の一言で終わらせないためにも宗教を見る目を養う必要がある。2013/02/10
けん
6
「10大宗教」でスルーされてた創価、オウム、幸福の科学について書かれています。現代社会において失われた中間共同体としての役割を持つ宗教団体は、今後も影響力を持ち続けるだろうというあたりまえのことを実感した。2011/04/03
-

- 電子書籍
- 後宮のポクチャ~下女から王の側室へ!?…