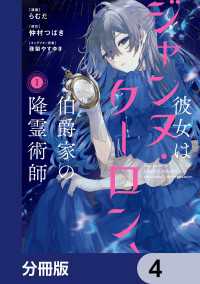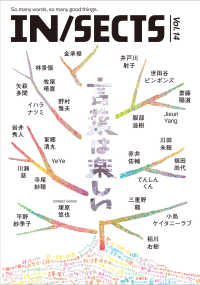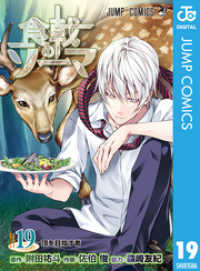内容説明
日本型生活保障の解体のなかで、噴出する人々の不安や「生き難さ」。「行政不信に満ちた福祉志向」が世論に強まるいま、日本政治は何をなしうるのか。戦後日本の、社会保障や雇用をめぐる政治すなわち福祉政治の展開を分析し、新たな視点から打開の道を探る。
目次
はじめに
序 章 日本の福祉政治──なぜ問題か,どう論じるか
第1章 福祉レジームと雇用レジーム
第2章 福祉政治をどうとらえるか
第3章 一九六〇・七〇年代の福祉政治──雇用レジームと福祉レジームの形成と連携
第4章 一九八〇年代の福祉政治──福祉レジームの削減と雇用レジームの擁護
第5章 一九九〇年代後半以降の福祉政治──雇用レジームの解体と福祉レジームの再編
終 章 ライフ・ポリティクスの可能性──分断の政治を超えて
あとがき
引用文献
さらに読み進む人のために
人名索引
事項索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
27
日本の福祉政治史を1960年代から今日まで考察し、今後の展望を簡単に示した内容となっています。分析枠組みとして「福祉レジーム」と「雇用レジーム」を示しています。日本社会が小さな福祉国家でしかなく、それを日本的慣行で補ってきたが、新自由主義的改革の中で「福祉レジーム」も「雇用レジーム」も成り立たなくなってきていることを指摘します。そして今後の方向性として生活のあり方そのものに関わる政治であり、ライフ・ポリティクスを重視し、福祉国家から福祉ガバナンスを目指す必要性を述べています。納得できない部分もありました。2017/12/21
佐藤一臣
6
日本の福祉は雇用の充実による家族主義を普遍化してきた。そこに世界的特殊性があるようで、そこから漏れた者が福祉に預かる感じらしい。ところが雇用体制が崩れだした現在、家族の解体と並行して生活の難しさが露呈し始めて来たようだ。雇用(賃労働+年金や社会保険料天引き)、失業手当、生活保護という3階層型のレジームが通用しなくなってきている。これからは雇用、失業、生活の中身を細かく見て制度設計する必要があると述べている。そのためには国に頼るだけでなく地方行政、民間を合わせた共同体の新しい形を作る必要があるらしい2023/03/25
ヒナコ
5
戦後日本社会の生活保障システムの変遷と、1980年代から始まる日本的生活保障システムの崩壊を分析した著作。 日本の生活保障システムのメインは雇用であり、雇用された「男性稼ぎ主」が家族賃金を獲得し、また企業から住宅手当や児童手当などを受け取ることで成り立ってきた。日本の生活保障システムのメインが雇用だったため、福祉としての生活保障システムは高齢者や障害者用の制度だけに限定されることになり、日本は世界的に見てずっと低福祉の小さな政府を続けていたと言える。→2021/07/17
Hiroki Nishizumi
3
日本社会では企業が社会保障を代行していることが今更ながら認識出来た。新自由主義が席巻する今、これからの展開がなかなか難しい気がする。2024/02/14
takao
2
ふむ2024/01/06