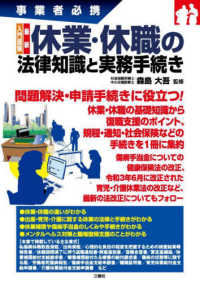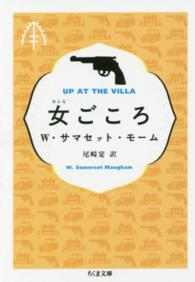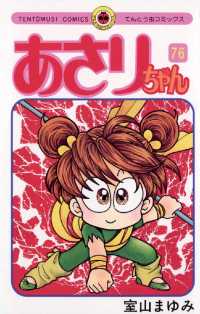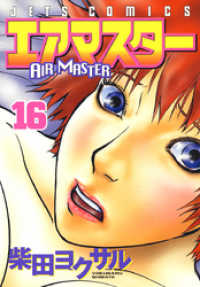- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
東京都新宿区と言えば、都会のど真ん中である。しかも、JR山手線の内側に、標高44.6メートルの「山」がある。その名は「箱根山」。箱根山と言えば、天下の険と言われ、現在でも温泉、秋の紅葉などで有名な、わが国有数の観光地である。それと同じ名前の「山」がなぜ東京にあるのか!ここに歴史の意外な秘密が隠されている。というのは、江戸時代から箱根は観光地として有名な場所。江戸の庶民にとっては遊山のメッカといってもよいところだった。武士も人の子。箱根に行ってみたいとは思うものの、そこは武士。なかなか庶民のように何日もかけて旅をし、観光を楽しむわけにはいかなかった。そこで、江戸に「箱根山」をつくり、何と武士が遊山ごっこをこの地でしたというのだ。要は江戸版スモールワールドである。本書では、いまも江戸の名残を止める「名所」を取り上げ、そこに隠された歴史の意外なウラ話を紹介した江戸ガイドだ。。
目次
第1章 江戸情緒あふれる名所へ(昔、本当に“三軒の茶屋”があった!?江戸の交通の要衝「三軒茶屋」―三軒茶屋;江戸の巨大遊郭「吉原」がもともと違う場所にあったワケ―千束 ほか)
第2章 歴史を彩った舞台をたずねる(「明暦の大火」の火元は本妙寺ではない!?まことしやかにささやかれる“火元引き受け説”―巣鴨;上野公園の不忍池が琵琶湖をマネてつくられたワケ―上野公園 ほか)
第3章 江戸っ子の生活風景を覗く(江戸の迷子専用掲示板だった「迷子しらせ石標」―日本橋;江戸時代には料金を徴収!?寛永寺にいまも残る「時の鐘」―上野公園 ほか)
第4章 江戸文化発祥の地を巡る(江戸っ子には門限があった!?夜十時には門が閉じられた高輪大木戸―高輪;『四谷怪談』で知られる「お岩稲荷」がなぜか四谷に二つもあるワケ―四谷 ほか)
第5章 武家社会の名残りをしのぶ(もともと、ふつうの町娘だった「護国寺」の創建者とは?―大塚;東京大学の「赤門」は江戸の婚姻政策のシンボルだった!?―本郷 ほか)