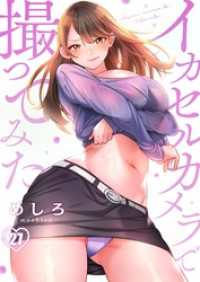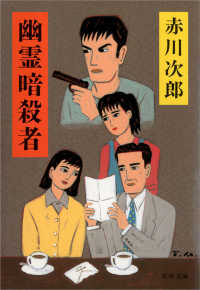内容説明
アフォーダンスとは環境が動物に提供するもの。身の周りに潜む「意味」であり行為の「資源」となるものである。地面は立つことをアフォードし、水は泳ぐことをアフォードする。世界に内属する人間は外界からどんな意味を探り出すのか。そして知性とは何なのか。20世紀後半に生態心理学者ギブソンが提唱し衝撃を与えた革命的理論を易しく紹介する。(講談社学術文庫)
目次
第1章 さんご礁の心理学
第2章 生きものはこのようにはふるまわない
第3章 「まわり」に潜んでいる意味―アフォーダンス
第4章 知覚する全身のネットワーク
第5章 運動のオリジナル
第6章 多数からの創造
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ばんだねいっぺい
22
足場となっている環境がアフォードしてくれる行為を変えたいとか、変化をさせたいのなら、環境を変えることは、知られているとおりその意味でも有効だ。ミミズって凄いし、ダーウィンの粘り強さにも感服する。2023/07/04
nbhd
19
ちょっと不満が残る本。「地面は人が立つことをアフォードする」とか、「水は人が泳ぐことをアフォードする」とか、世界認識を180度回転させそうな予感のするアフォーダンスなる概念を紹介しているのだが…確かに、身体はある程度環境に制御されてて、思考を通過せずに何らかのアクションをおこしているとは思うのだけど(=身体知)、結局それも認知科学(脳機能)の領域を出ないわけで…。アフォーダンスのキラキラ感を味わえると思ったら、「結局、脳の話じゃん!」っていう肩透かしをくらったかんじ、というのが僕なりのせいいっぱいの理解。2016/01/25
galoisbaobab
14
アフォーダンスって概念は分かったような気がしてやっぱり分かってない気がしていつももやもやしちゃうんです。アフォーダンスを文学的なポテンシャル場と思ってはいけないし、しかし自分から外にはみ出しちゃった”意味”を計測するために「行動を観察する」ってなんか逆なような気がするし、ふに落ちるまでにはまだ時間がかかるんでしょう・・・(頭わるっ)2017/11/22
武井 康則
12
その環境の影響によって行動に変化が起こるし、第一行動を喚起するかもしれない。それが環境のアフォーダンス。それを受けて相互の影響が相互の行動となって、思考となる。目的を実行するのでなく目的がその場で作り出されていく。では、目的が会っての行動は、それは社会とか政治の、言わば人工的なもので、まず原初的な環境との接触が思考を生んでいくのだと読んだのだけど。2020/02/01
eirianda
11
環境の変化に慣れるということは、脳内だけで処理されるのではない。ということでアフォーダンスを理解していると思っていいのだろうか? コロナ禍で目に見えないウイルスに立ち向かう今は、理屈でしか動けないのだけれど。ミミズのように柔らかい土を探り生き延びたい。2020/12/11