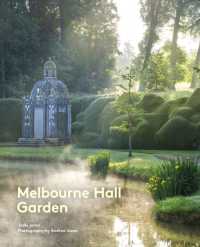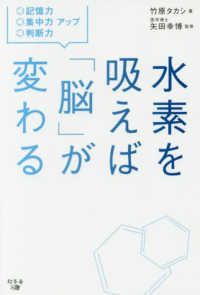内容説明
国語教育こそ「愛国教育」である。倫理の領域に踏み込む「道徳教育」は教室になじまない。学校に過剰なサービスを期待してはならない。……西洋は古代ギリシャから近代アメリカまで、日本は鎌倉時代から明治時代まで、東西の教育史をつぶさに検証。文明と教育との深い関わりを鮮やかに解き明かした上で、明日の日本のため、さまざまな提言を大胆に行う。中央教育審議会会長による画期的な教育論。
目次
序章 荒廃のなかの教室―私に「教育の原風景」を与えた敗戦後の満州。
第1章 学校教育はなぜ必要なのか―現実は「経験」によっては学べない。
第2章 文明とともに―文明と教育は武力にまさる。
第3章 古代ギリシャから中世へ―教育に見るヨーロッパ文明 多様の統一。
第4章 ルネサンスからの歩み―国民国家と義務教育へ。
第5章 鎌倉、室町、そして江戸―日本の文明は、アジアでなく、じつはヨーロッパと共通している。
第6章 近代国家の成立に伴って―世界文明の統一の趨勢のもとで。
第7章 統治とサービス―現代の教育機関は社会から過剰にサービスを求められてはいないか。
第8章 国語、道徳、歴史―内面的な倫理意識に踏み込む「道徳教育」は教室になじまない。
終章 明日に向けて―教育の限界を認め、「驕りなき教育」をめざさなければならない。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kubottar
19
現代の教育が国家の提供するサービスになってしまったことは興味深い。2021/02/05
佐藤一臣
17
論理的な主張を展開する中で、実例や証拠のないところが前半部分は多くあったのが残念。大量消費・権威主義・学歴主義は悪いと思われているが、それを当時社会が選んだ理由が問題解決のためだったことを忘れてはならないという視点には賛同。所謂苦痛の除去が最大理由であるということ。どんどん秘密⇒公開の世の中になり、法制化・制度化で縛らないと社会が崩壊するかもという危惧不安に陥ってしまうんでしょう。ある歴史学者が言っていた「歴史上の偉人が歴史を作ったのではなく、名もない人々の集合体が歴史を作った」ことを忘れちゃだめですね。2017/10/25
ごへいもち
16
訃報に接してもう3年も経ってしまった、合掌2023/11/04
ひよピパパ
12
教育の本質について、教育思想史の流れを踏まえつつ捉え直した書。部活を社会に解放する等の首肯できる提言はあるものの、現場に即した具体的な議論になっていないのが残念。2022/05/04
みのくま
12
序章だけ読めばそれで良い気がする。 満州国崩壊とその後の学校教育を著者自らの体験として書かれた序章は面白かった。 ただ、それ以降は20年前30年前の教育論でよく聞いた内容だったと思う。 また、それこそ学生一人一人の承認の問題を全く無視していて、全くアクチュアルではないなぁと。 教育論のような二項対立がある意見で中庸ばかり諭されても面白くない。第三項を提出するような冒険がほしい。2017/05/05