- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
二〇〇五年から始まった日本の人口減少。一〇〇年後には半減と予測されている。北・西ヨーロッパに端を発し、いまや世界人口の半分を覆った少子化は、なぜ進むのか――。急激な人口減少が社会問題化するなか、急速に脚光を浴びる人口学だが、戦前の国策に与したと見られ、近年まで疎んじられてきた。本書は、人口学の入門書として、人口の基礎的な考え方、理論、研究の最前線、少子化のメカニズムなどを平易に解説する。
目次
序章 人口問題-急増から激減へ
第1章 人口学の基礎
第2章 生命表とその応用
第3章 少子化をめぐる人口学
第4章 人口転換-「多産多死」から「少産少死」へ
第5章 生殖力と出生率-生物的・行動的「近接要因」
第6章 結婚の人口学-非婚・晩婚という日本的危機
第7章 出生率低下と戦後社会-五つの社会経済的理論
第8章 出生率の予測-可能性と限界
第9章 将来の人口推計-未来をよむ人口学
終章 人口減少社会は喜ばしいか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Haruka Fukuhara
13
世界の人口学をリードしてきたのはアメリカとフランス。アメリカは実証主義的、社会学系の社会人口学、フランスは理論的・論理的に明晰なタイプの人口学においてそれぞれ業績を上げてきた。日本では歴史人口学以外はほとんど認知されていない。といった概観を知ることが出来たのが一番興味深かった。2007年。2005年から、1年予想より早く日本の人口減少は始まったとのこと。米仏の人口学の代表的教科書が手に入れば目を通してみたいところ。2017/05/26
Francis
9
人口学の入門書。世界的に少子高齢化は進んでおり、最近のアジア諸国ではそのスピードが欧米のそれよりも早いとのこと。ヨーロッパでは英仏、ベネルクス、北欧諸国のように個人主義的な家族形態を取る諸国が権威的な家族形態をとる他のヨーロッパ諸国よりも高いことは特筆に値する。人口は一旦減少に転じると増加傾向に戻るのは難しいので、余力のあるうちに少子化対策をするべきとも。大学時代に講義を受けた大淵寛先生の名前がちらりと出たのが個人的には嬉しかった。2016/05/17
youmaysay
6
日本で今後少子高齢化が進むということは誰でも知っているが、それゆえにそこで止まってしまって学問としての人口学に興味を持つ人は少ないのではないだろうか。人口変化が慣性を持っているというのは興味深く、マイナスの慣性が大きくついた日本の人口減少に歯止めをかけるのは不可能にも思える。2017/01/28
イシコロ
5
前半は現実を写し出すために試行錯誤していく、統計への真摯な態度を見せられた。 ただ統計についてを解釈する段になると、どれもそうでしょうねという感じ。未来へ示唆を得るにはまだまだ成熟が必要な学問だと思います。2025/01/26
朝ですよね
5
最新のコーホート合計特殊出生率を調べてみると、令和3年における35~39歳の世代の39歳までのは1.45だった。出版(2007)の頃から期間合計特殊出生率は下げ止まっており、晩婚化影響が薄まっていると解釈できそう。同じ人間でも社会的な背景が異なっているため、人口学では国際的な統一理論のようなものは確率が難しいようだ。移民に関する記述は殆どなかった(海外事例でも)。OECDによる出生率回復シミュレーションが興味深かったものの、本書にある2005年のもの以降の類似する研究は見つからなかった。2023/06/08
-
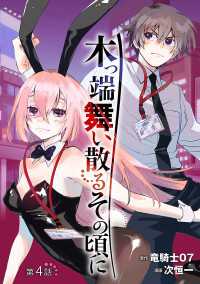
- 電子書籍
- 木っ端舞い散る その頃に(話売り) #…
-
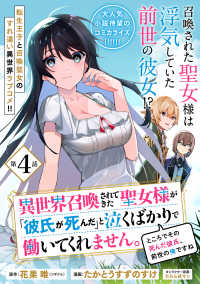
- 電子書籍
- 異世界召喚されてきた聖女様が「彼氏が死…
-
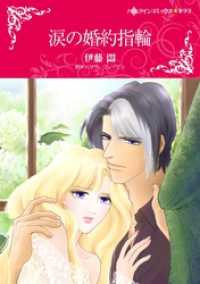
- 電子書籍
- 涙の婚約指輪【分冊】 1巻 ハーレクイ…
-

- 電子書籍
- 乗取り - 傑作企業小説 光文社文庫
-
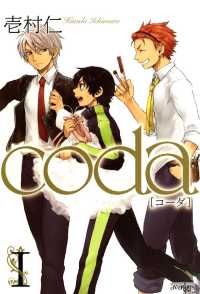
- 電子書籍
- coda(1) 月刊コミックアヴァルス




