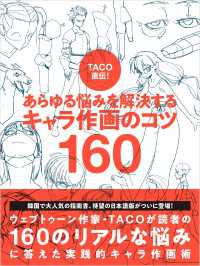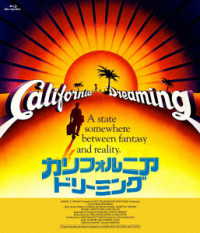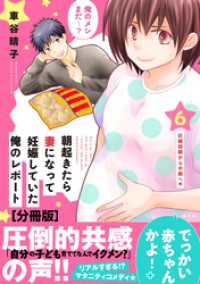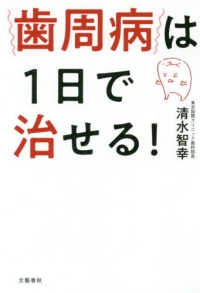内容説明
朝廷・公卿・武門が入り乱れる覇権争いが苛烈を極めた、激動の平安末期。千変万化の政治において、常に老獪に立ち回ったのが、源頼朝に「日本国第一の大天狗」と評された後白河院であった。保元・平治の乱、鹿ヶ谷事件、平家の滅亡……。その時院は、何を思いどう行動したのか。側近たちの証言によって不気味に浮かび上がる、謎多き後白河院の肖像。明晰な史観に基づく異色の歴史小説。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
352
まず目につくのは「語り」である。権力者の傍近くにいた者が往時を回想し、話体で語るのは芥川の「地獄変」の手法であった。また、複数の証言から物語世界を浮かび上がらせるのも、これまた芥川が試みた「藪の中」に他ならない。もっとも、本編はそうした先蹤にとどまらず、もう一つの装置を有していた。実記である。平信範の『兵範記』、吉田経房の『吉記』、そして九条兼実の『玉葉』がそれである。(建春門院中納言については出典は不明)。ただし、史実に忠実に立脚しているようでありながら、そこにはフィクションが巧みに介在する。⇒2017/12/01
新地学@児童書病発動中
113
混沌とした平安末期をしたたかに生き抜いた後白河院の肖像を描く歴史小説。馴染みのない歴史的な用語が多く出てくるし、さまざまな人物が入り乱れて登場するのでやや読みにくいが、面白い。この小説の一番の特徴は、後白河院を四つの人物の視点から浮き彫りにしたことだろう。どの人物から見ても後白河院には謎めいたところがあり、彼の胸の内ははっきりしない。ある時は優しい父親、ある時は気高い貴人、ある時は優柔不断な貴族に見える。一番私の胸に沁みたのは権力者としての孤独であり、それは多くの現代人が共有できるものだと思う。2015/03/08
優希
58
激動の平安末期に「日本一の大天狗」と言わしめられた後白河法院。そのあり方を4人の側近たちの語りによってぼんやり且つ不気味に浮かび上がらせているのが印象的でした。謎多き後白河法院の肖像を史観的に描いた歴史小説だと思います。2023/01/21
優希
51
面白かったです。激動の平安末期、常に立ち回ったのが後白河院でした。4人の語り手によって紡がれる後白河院が「日本第一の大天狗」と源頼朝に称されたのも納得です。不気味に浮き上がる肖像は不気味な香りをも放っていました。2022/06/23
Gotoran
44
朝廷・公卿・武門が入り乱れる覇権争いが苛烈を極めた、激動の平安末期。千変万化の政治において、常に老獪に立ち回り、源頼朝に「日本国第一の大天狗」と言わしめた後白河院について、4人の貴族を語り部として、物語は進行していく。平治の乱から頼朝将軍宣下の直前までの激動の時代に後白河院が何を思い、どう行動したかが4人の側近の証言を通して浮き彫りにされる。2024/12/18