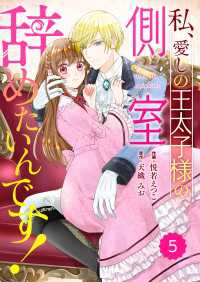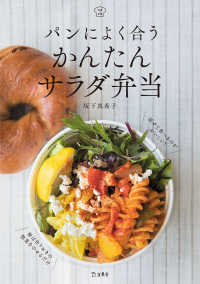- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
細川連立政権崩壊から一〇年以上が過ぎ、日本政治は再び自民党の長期政権の様相を呈している。しかしその内実は、かつての派閥による「支配」とは全く異なる。目の前にあるのは、一九九〇年代半ばから進んだ選挙制度改革、政治資金規正法強化、行政改革などによって強大な権力を手にした首相による「支配」なのだ。一九九四年以降の改革のプロセスを丹念に追い、浮かび上がった新しい日本の「政治体制」をここに提示する。
目次
序章 新しい政治の幕開け
第1章 自民党の政権復帰と新進党の結成
第2章 橋本内閣と行政改革
第3章 新進党の崩壊と民主党の台頭
第4章 小渕恵三・森喜朗内閣―過渡期の政権
第5章 小泉純一郎と首相権力の確立
第6章 参議院という存在
第7章 郵政民営化と権力の行使
終章 権力の一元化と二〇〇一年体制の成立
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
18
なぜ安倍政権の一強状態が続くのか。理由は2001年体制にある。2001年体制以前は、中選挙区・派閥政治中心の55年体制だった。派閥中心なため、自民党総裁=首相の権限は弱く、行政機構も20を超える省庁が存在し、特に大蔵省が大きな権限を持っていたため、首相の権限は低かった。2001年体制は、94年の選挙制度改革と政治資金制度改革→96年の橋本行革→05年の郵政選挙を経て確立した。小選挙区制により、総裁が公認権を独占し、政治資金制度改革により、派閥が政治資金を集めにくくなる一方、政党そのものは集めやすくなった。2016/08/21
あんころもち
9
小選挙区制導入、内閣強化、自民党総裁選における予備選導入から小泉政権の「成功」、とりわけ郵政民営化実現に至る過程を物語風に解説。あんまり細かいこと書かずにザックリと内閣機能の強化についてまとめた本なので、類書の中では最も読みやすい。首相個人の人気や能力が政権の基盤に直結するようになったため、能力のない人が首相になったら悲惨という指摘はまさにその通り。2016/08/16
バルジ
5
1990年代から2000年代前半の日本政治を首相の制度的指導力を軸に描く。刊行から15年以上経つが政局も盛り込んだその政治学的分析は色褪せない。55年体制の終焉から仁義なき政権争奪、行革を引っさげて現在につながる首相権力の制度的強化と省庁再編を行った橋本龍太郎、その橋本の行った「政治改革」の果実を享受し強化された首相権力をフルに活用した小泉純一郎。時に剥き出しの権力闘争を孕みながらダイナミックに動く政治を「首相支配」という観点で分析する。小泉政権以後の「首相支配」に相貌も増補版とし読みたいところ。2021/06/03
Kentaro
5
1990年代半ばから進んだ選挙制度改革、政治資金規正法強化、行政改革により、首相が強大な権力を持つようになったというのが著者の見方である。かつては派閥の長に集金が集まった世界から政党助成金による選挙資金の配分が行われたことも、派閥から党トップの意向が反映させられるように変えてしまった。さらにねじれ国会に代表される参議院の過半数をとらなければ政策の良し悪しにか変わらず、法案が通らないという多数派工作が必要になり、過半数をとるために小政党の離合集散が盛んになり、理念なき離合集散も度々行われた。2018/11/06
じ
3
1990年代後半の政治・行政改革による政治の変貌を、新聞報道等も豊富に用いながら明らかにする。竹中治堅すごい。2020/01/18