- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「作家の発言は多かれ少なかれみんな嘘だと思っています」。そう語る本人が25年間ついてきた<嘘>――「日本の小説はほとんど読まなかった」。作品にちりばめられた周到な仕掛けに気づいたとき、村上春樹の壮大な自己演出が見えてきた。しかしそれは読者を煙に巻くためだけではない。暗闘の末に彼が「完璧な文章と完璧な絶望」を叩き込まれ、ひそかに挑んできた相手はだれか? 夏目漱石、志賀直哉、太宰治、三島由紀夫……。「騙る」ことを宿命づけられた小説家たちの「闘いの文学史」が、新発見とともに明らかになる![小説家という人種]「志賀直哉氏に太宰治氏がかなわなかったのは、太宰氏が志賀文学を理解していたにもかかわらず、志賀氏が、太宰文学を理解しなかったという一事にかかっており、理解したほうが負けなのである」(三島由紀夫)……そんな三島こそ太宰の最大の理解者だったのでは? そして、その三島由紀夫の最大の理解者は?
目次
序となる文章 「巨大な事物の真実は現われにくい」(村上春樹)
第1部 闘いと迷宮と―新しい“村上春樹”の発見(ある闘いの文学史―志賀直哉・太宰治・三島由紀夫 太宰と三島という「二」の問題―『風の歌を聴け』 「三」という出口へ―『1973年のピンボール』)
第2部 世界分裂体験―村上春樹とその時代(「鏡の中」の異界の問題―『羊をめぐる冒険』 脳と意識の微妙な関係―『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』 「死=生」を描くリアリズム―『ノルウェイの森』を中心に)
第3部 世界を含む世界へ―『豊饒の海』から読む村上春樹(「『絶対の不可能』=可能」という主題―『春の雪』と『ノルウェイの森』 「幻でないものがほしい」―『ダンス・ダンス・ダンス』と『奔馬』)
終わりとなる文章 「(小説家は)理解したほうが負けなのである」(三島由紀夫)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とくけんちょ
いろは
ケイ
501
佐島楓
-
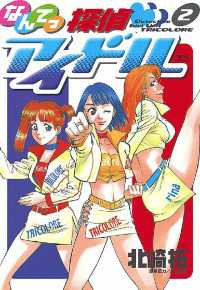
- 電子書籍
- なんてっ探偵・アイドル(2) ヤングサ…
-
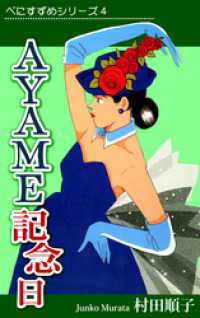
- 電子書籍
- べにすずめ4 / AYAME記念日
-

- 電子書籍
- マーダーライセンス牙(18)
-
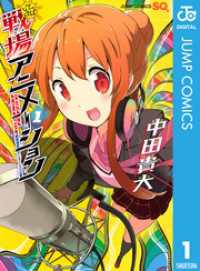
- 電子書籍
- 戦場アニメーション 1 ジャンプコミッ…
-
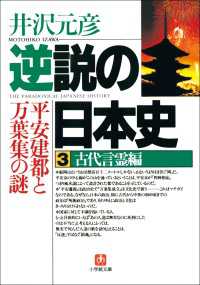
- 電子書籍
- 逆説の日本史3 古代言霊編/平安建都と…




