- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
20世紀に描かれた絵画は、それ以前の絵画が思いもしなかった無数の認識をその背景に持っている。「具象/抽象」「わかる/わからない」の二元論に別れを告げる新しい美術史。
目次
序章 『モナリザ』も『黒に黒』もわからない?(わからないから嫌い? 新たな謎 ほか)
第1章 抽象絵画の成立と展開(平べったい裸婦―マネ『オランピア』 行く川の流れは絶えずして―モネ『陽を浴びる積み藁』 ほか)
間奏 “旧東独美術”の見えない壁
第2章 具象絵画の豊饒と屈折(風景の形而上学―ベックリン『死の島』 揺れる自意識―ムンク『叫び』 ほか)
終章 「わかる」ということ(「わかる抽象」と「わからない具象」 『ニュルンベルクのマイスタージンガー』 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
koke
12
再読。タイトルこそシンプルに「20世紀絵画」だが、マネ・モネにはじまる一見オーソドックスな前半に対して、後半は従来の美術史になかった旧東独美術を大きく扱っている。モダニズム美術史を一度インストールした者にとっては驚くような論展開であり、驚くような具象表現の氾濫だ。著者の狙いは「具象/抽象」「わかる/わからない」の二項対立を崩すことにある。具象/抽象にかかわらず絵画は見るものに思考を要求する。そのことが著者自身の経験に基づいて示される。好き嫌いで終わらないから美術は面白いのだと再認識した。2024/11/14
もよ
12
ヨーロッパ至上主義的かつ前時代的上から目線や偏った守備範囲が気になりました。さらに、フランシス・ベーコンに触れられていなかったり、アンゼルム・キーファーが彫刻を作っていないような記述があったりと不備も。 タイトルや序文と中身もあまり一致していない感じがしました。2016/11/01
giant_nobita
11
抽象絵画/具象絵画という20世紀絵画の2つの流れのうち、前者のほうは馴染み深い。絵画とは何かを問う発展史として理解することができるからだ。それに比べ後者は、抽象絵画のあとに具象絵画を描くことが、ともすれば反動や後退と映ってしまう。しかし本書では、著者が関心を寄せる旧東独の画家を中心に、「国家とは何か、わたくしとは何か」を問いかける具象絵画の可能性が追求されている。そうした探求の果てに、著者自ら「わからない」と混乱する具象絵画が、解決されない謎としてわれわれ読者の前に差し出される。2018/01/03
morinokazedayori
9
★★★★★絵画鑑賞の醍醐味は、感覚的な「好き嫌い」にとどまらずその絵画を正しく「理解する」ことであり、人間関係同様相手を「わかる」ことで単なる「好き嫌い」以上のより深く分かちがたい関係を築けると著者はいう。 本書の軸になっているのは抽象と具象の二元論だが、二次元と三次元、物語性とコンセプチュアルなど、絵画における様々な対立概念も紹介されており、20世紀絵画史を俯瞰できる。作品の成立には社会的風潮・思想・時代背景などが深く関わっており、絵画が視覚的な快・不快を超えた時代時代の一つの結晶であることがわかった。2015/11/17
yo27529
5
意外と難解な表現にしばらくぶりに遭遇しました。よく理解できたとはとても思わないのだけれど、後半の具象絵画の章は圧巻。ドイツ美術から20世紀美術を問い直しているともいえる。おかげで知らない画家に沢山めぐり合いました。ネットの時代なのでネットで紹介されている絵を検索して鑑賞しながら読書しました。これからはこんな読書もいいかもしれない。2013/12/09
-
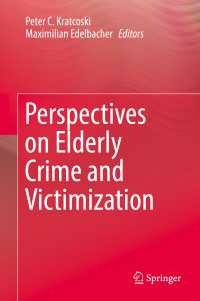
- 洋書電子書籍
-
高齢の犯罪者・被害者に関する考察
-
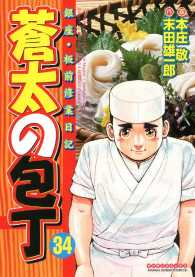
- 電子書籍
- 蒼太の包丁34 マンサンコミックス







