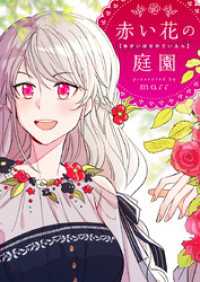- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
建築とは何か、その歴史とはどのようなものだろうか? 母なる大地と父なる太陽への祈りによって誕生した〈建築〉。地母神が人をやさしく包む母のような内部を、太陽神が人の眼前にそびえる父のような外観をもたらした。以降、神々のおわす神殿、神社へと発展し、青銅器時代から二十世紀モダニズムへと駆け抜けていく。人々の共同意識が作り出し、さらに意識を組織化する力をもつ建築。様々な説により自由にかつダイナミックに展開する、全く新しい『初めての建築の本』。
目次
第1章 最初の住い
第2章 神の家―建築の誕生
第3章 日本列島の住いの源流
第4章 神々のおわすところ
第5章 青銅器時代から産業革命まで
第6章 二十世紀モダニズム