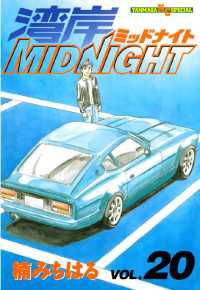- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
『徒然草』を教科書では、「無常観に基づいて人生観を綴った随筆」と教える。しかし、それだけでは読みが浅い。現代人のコミュニケーションやビジネスにも使えるヒントが満載されているのだ。たとえば、「初心の人、二つの矢を持つ事なかれ」(初心者が二本の矢を持ってはいけない)という第九十二段では、「集中力を高める」秘訣を教える。また、「偽りても賢を学ばんを、賢といふべし」(たとえ本心でなくても賢人に学ぶ人が賢人である)という第八十五段では、真似ることで技が磨かれるという。『徒然草』は上達論として読める古典なのだ。その他にも、「自分の得意技を持て」「眼力をつける」「知ったかぶりをしない」「嫌な気分を整理する方法」など、先人の智恵から多くのインスピレーションが得られる。「古典はムリヤリにでも自分にひきつけて“使う”というくらいの気持ちで迫るのがちょうどいい」と著者は語る。教科書では教えない「平成徒然草」の読み方を紹介する。
目次
序 『徒然草』の使い方
第1章 上達の秘訣(やりたいことはすぐ取り掛かる―第百五十五段 真似ることで上達する―第八十五段 人前に出て、技は磨かれる―第百五十段 ほか)
第2章 生きるのが楽になる知恵(三人の先達を持つ―第五十二段 勝手な行動が許されてしまう人―第六十段 眼力をつける―第百九十四段 ほか)
第3章 人生を深く味わう極意(大欲と無欲は同じ―第二百十七段 孤独を技にして、自らを深める―第七十五段 余韻を残す心遣い―第三十二段 嫌な気分を整理する方法―第十一弾)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
シュラフ
30
『徒然草』は折に触れて手に取りたい書である。ふだんせわしなく活動して我を失っている我々凡人が自分を取り戻す機会になる。第75段では「つれづれわぶる人は、いかなる心ならん。まぎるる方なく、ただひとりあるのみこそよけれ。」とある。常に誰かと一緒にいなければ落ち着かないという心理がある。だけれどもたまには自分ひとりの時間を持てよ。独りになってみて、本を読んでみたり、考え事したりして自分をクールダウンしてみよう。きっと周囲に流されているだけの自分自身が客観的に見えるはず。つれづれというのは大切な時間なのである。2018/02/25
京和みかん
17
この本は、『徒然草』がいかに現代社会に役立つか、という内容の本です。著者の斎藤孝先生は教育学者です。ですから、教育という観点からも徒然草を読み取っているのがよく分かります。本書で齋藤先生は「徒然草は古典ではなく人生の使える基本書」だと述べています。人生の様々な場面で、徒然草を思い出すようなシチュエーションがあるのです。その際には、徒然草の兼好の言葉を思い出すと、人生の考え方が楽になることでしょう。徒然草の紹介と共に、人生の生き方を教えてくれる一冊です。2016/12/18
Lee Dragon
16
なんと刺さる箴言の数々。道場に通って稽古した気になってるのダメだぜ的な台詞刺さりまくる。孤独こそ人を豊かにする。 去り際の残心(お見送り、お土産)を日々の習慣にすることで、相手の心に残る人になるのはめちゃくちゃ共感した。2023/04/26
とよぽん
13
鎌倉時代後期、隠者となった吉田兼好の随筆が、約700年を経た現代の中学生に、どのように読まれるか? 国語の授業で「仁和寺にある法師」と、他にいくつかの章段を取り上げたいのだが・・・。難しいかな?2017/07/28
獺祭魚の食客@鯨鯢
12
荻野文子氏の「ヘタな人生論より徒然草」と比べると、原文掲載ということもあり、オーソドックスな感じを受けます。古典は「スルメ」のように噛めば噛むほど味わい深くなるという言葉通り、同じ段でも荻野作品と解釈や評価が微妙に異なっていて、興味深くよむことができます。原文を訳出せずにそのまま味わうことが出来たらどんなに素晴らしいことだろうと思います。これは英文学にも言えることです。日本人のリテラシーが翻訳や解釈に偏り素直の作品を味わうことができないほど低いことを感じざるを得ません。2018/02/12



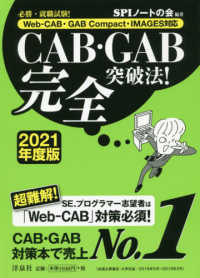
![[合本版]神曲奏界ポリフォニカ ブラックシリーズ 全14巻 GA文庫](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0249833.jpg)
![[合本版]EX! 全15巻 GA文庫](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0249835.jpg)