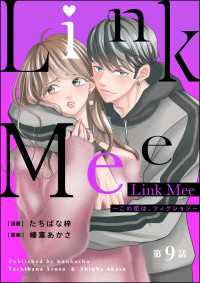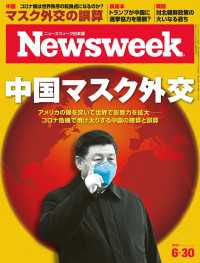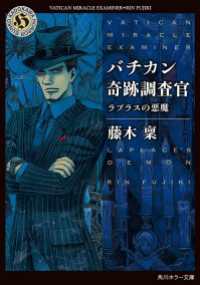- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
文部科学省のゆとり教育政策のもと、日本の子供たちの学力低下が大きな問題となっている。
では、詰め込み教育に戻ればいいのか?パラダイムが一変した現代社会を生き抜くためには、知識を修得するだけではなく〈疑う力〉を鍛えることが必要なのである。
“疑う力”があれば、新しい発見をすることができる。
リスクに備えることができる。
対人関係がうまくいく。
人生のビッグチャンスをつかむことができる。
学校では教えてくれないノウハウを満載した和田式勉強法の最新バージョン。
学校で教わらない「考える力」をつけるために必要不可欠な<情報を疑う力><真偽を確かめる力>の思考訓練法を具体例を挙げて紹介。
文部科学省のゆとり教育政策のもと、日本の子供たちの学力低下が大きな問題となっている。では、詰め込み教育に戻ればいいのか? 旧来型の受験勉強で頭がよくなるのか? 21世紀は脱学問の時代とよくいわれる。このようなパラダイムが一変した現代社会を生き抜くためには、情報を修得するだけでは不十分である。情報を活用する能力だけでも不十分である。これからの時代はさらに「情報を疑う能力」が必要なのだ――というのが本書における著者の提言である。情報の修得技術、活用技術を磨けば、いわゆる問題解決能力を高めることができるが、これからはさらに「問題発見能力」の優劣が問われるということだ。<疑う力>があれば、新しい発見をすることができる。リスクに備えることができる。対人関係がうまくいく。人生のビッグチャンスをつかむことができる。学校では教えてくれないノウハウを満載した和田式勉強法の最新バージョン。
●第1章 情報を疑う能力が問われる時代
●第2章 何が疑う力を奪うのか
●第3章 疑う力が判断をより妥当にする
●第4章 疑う力が創造性を養う
●第5章 疑う力でこれからの世の中を読む
目次
第1章 情報を疑う能力が問われる時代(メディアが「疑う力」を奪っている;スケープゴートを作る論調に流されるな ほか)
第2章 何が疑う力を奪うのか(心情読解問題への疑問;子供の疑問にはきちんと答えること ほか)
第3章 疑う力が判断をより妥当にする(自分の力に疑いを持つ;メタ認知の大きなメリット ほか)
第4章 疑う力が創造性を養う(発明、発見のきっかけ;問題解決能力と問題発見能力 ほか)
第5章 疑う力でこれからの世の中を読む(企業不祥事はなぜ起きる?;学力低下はなぜ生じたのか? ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ハッシー
テツ
Q
サトシ人生サボらない隊
わえ