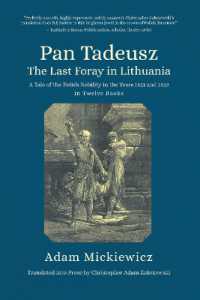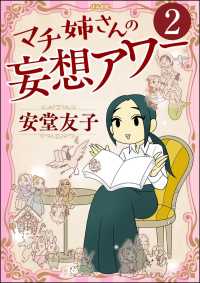- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
人に教えたくない店は、表通りより、路地を入ったところにある、などとよく言われる。それは会話についても言えるのではないだろうか。一つのテーマに沿って延々と続く議論を聞き続けるのは苦痛なことだ。路地裏のいい店の喩えではないが、ときに話が本題から反れる。その話のほうが面白いということはよくあることだ。本書で御両人が語り合っているテーマそのものは日本文化論に通じるものあり、精神史に通じるものありで、その意味では正攻法の対論である。しかし、自分の幼児期の体験、青春時代の思い出などを織り交ぜた会話は、知的な漫才のような面白ささえ感じる。まさに、裏路地の会話、である。その会話には、示唆にとんだ一言あり、正鵠をついた社会批判ありで、読む者を飽きさせることがない。こういう会話を知的な会話というのだろう。ご両人と寄り道しながら、日本人とは何か、信仰とは何かなど、重いテーマを軽く楽しんで見てはいかがだろう。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ちさと
22
それぞれ昭和3年、12年生まれの御二方のお話は、小さい頃にお爺ちゃんのお話を聞いていた場面を思い出す。生まれから学生時代、教授時代へと、お互いの精神形成史を語り合う前半と、大きくたくさん刻まれた年輪を見せてくれる後半に分かれています。テーマごとに連歌連句になりがちな対談ですが、意見の相違がちらほら見受けられるところが良かった。養老さんの「肩書きがないことを嫌う社会」森さんの「未来を築くはみ出し者を容認しよう」2018/11/09
toshi
8
リレーエッセイだけど、後書きによれば一日で行われた対談らしい。 いろんな話題で盛りだくさんの内容で、色々考えさせられる。いかにもPHPらしい本。2016/02/28
PPP
5
★★★☆☆:昭和3年生まれの森氏と昭和12年生まれの養老氏の対談本。前半は「世間が違えば標準が違う」(戦争の影響)、「肩書がないことを嫌う社会」(人間関係の距離の明示)など、時代・文化について。後半は「あらゆることが説明できるという幻想」(科学信仰)、「三島の自殺とオウムで見えてくる世の中の構造」(世間の無自覚)など、脳・精神について。ーー人世は、論理的に説明できないものの方が遥かに多く、組織・保障・システムなどに囚われ過ぎると、結果自分で自分の首を絞めることになる。2016/09/19
かりんとー
4
とにかく自分の頭で考えること。 危機のときにマニュアルを捨てることができるか? 「ああすればこうなる」という意識化された世界に 暮らしていると、危機管理能力が発揮できない。 予想される危機は本当の危機ではない。 人間のつくったものを頭から信奉するようなことは避けるべき。 がちがちの「システム」からの脱出が閉塞感を打ち破る鍵になる。2014/07/21
柊
3
養老孟司氏と森毅氏の対論本。本書では、現代人の抱えるジレンマ的思想や、脈々と受け継がれる「非国民」の文化、「逃げられない」社会を解剖していく。 非常にテンポが良く、読むと元気づけられたり、襟を正したくなったりと身になる濃い内容。 特に連歌連句から続く「場の文化」という考え方にはうなずくばかり。人と話すことでブレイクスルーって生まれるよね。 2014/06/17