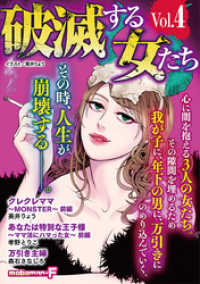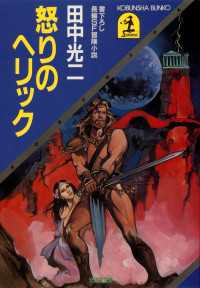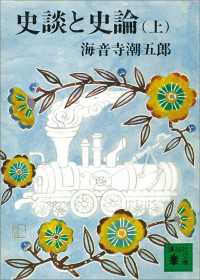内容説明
いま、改めて富士山を知る――。著者の「富士山もの」の掉尾を飾る傑作。
霊峰富士に対する民間信仰は昔からあるが、急速に大衆化したのは「富士講」の始まった天正年間である。しかし、大衆化は同時に信仰の俗化、形骸化を招いていった。富士講の荒廃に反発する行者・月行に見出され、のちに富士講中興の祖と称されるまでになった身禄の、感動的な波乱の一代を描いた長篇歴史小説。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mura_ユル活動
98
新田次郎、21冊目。彼の小説で富士は3冊目。江戸時代、富士講。伊兵衛は富士講六世を継ぎ、身禄となり、入定し31日遷化(せんげ)。富士講の実話。もう1人の六世村上光清のきらびやかな富士講との対比。家族の問題・商人で苦労・第5世の月行とのやり取りに多く頁を使っていて、心境の細やかな変化をつかむ。ご利益目的の信者は求めない、最終的には身禄の富士講に人は集まる。「食べるために生きるのか、生きるために食べるのか」「人間のできることには限りがある。欲張ってはならない」。新田次郎では5番内に入るほどよかった。2019/12/07
yoshida
96
霊峰富士への民間信仰「富士講」。その始まりは天正年間。富士講中興の祖である身禄の生涯を描く。富士講は月心と月光の二派に別れた。月心は大衆に教義を説き弟子や信者を増やす。月光は修行に打込む。商人の伊兵衛は月光に命を救われ、次第に富士講に惹かれる。遂に月光の弟子となり、身禄として跡を継ぐ。その過程で婿となった商家を追われ油商となる。生業と修行に打込む身禄を労咳が襲う。月心派は光清が継ぎ大名と呼ばれる程の富貴となるが、教義は乱れた。身禄は乞食と呼ばれるも入定で始めて教義を説き興隆を迎える。知見を得る読書時間。2021/12/14
大阪魂
57
新田さんの「富士山もの」5作の一つ。歴史小説&プチ山岳小説。富士山に参拝に登る「冨士講」。江戸時代はブームなったそうなんやけど、その中興の祖って伊兵衛=6世食行身禄の伝記。5世のとき大衆に迎合、山を稼ぎ場にさせてしもた?月心と、独り修行して地震や噴火を予知した月行に別れ、たまたまの出会いで伊兵衛は月行の弟子に。商人としても成功しつつ、行者としては営利に走らず教義なかった富士講に「誠の心」を柱とした教えを確立、富士で入定(=宗教的自殺)しはったから大ブームに!こんな歴史あったんやねー!他の富士ものもよも!2021/12/14
金吾
31
○身禄という人物を知らなかったのですが、その清廉な生き方に感銘を受けました。信念のすごさを感じます。入定の描写は真に迫りました。2025/04/01
ちゃま坊
28
江戸時代の富士山信仰のブーム。富士講の行者はまるで天狗のようだ。信仰を餌とし、お山を稼ぎ場と心得る輩の初穂代の奪い合い、山役銭を取り合う人々への富士の怒りが噴火大爆発か。過度に宗教や観光で稼ぐことへの批判とも取れる。狂犬病被害の話が出てきたが、綱吉の生類憐れみの時代背景と関係する。2020/07/22