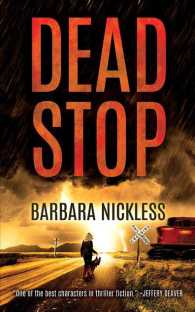内容説明
“風の吹溜まりに塵芥が集まるようにできた貧民街”で懸命に生きようとする庶民の人生。――そこではいつもぎりぎりの生活に追われているために、虚飾で人の眼をくらましたり自分を偽ったりする暇も金もなく、ありのままの自分をさらけだすしかない。そんな街の人びとにほんとうの人間らしさを感じた著者が、さまざまなエピソードの断面のなかに深い人生の実相を捉えた異色作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ミカママ
478
戦後それほど時代の経っていないと思われる、とある町の長屋舞台の短編集。この長屋の住人たちがことさら貧しかったというわけでもなく、おそらく日本中がまだまだこんな感じだったんだろう。どれも読み終わってかすかな郷愁&既視感を感じる…日本人の根底を描いているからだろうな。映画『どですかでん』の原作を奇しくも読め、開高健の親しみにあふれた解説も良い。山周さんにはもう少し女性を勉強して欲しかったところだが、言っても詮ないことだ。2021/01/16
ヴェネツィア
291
『青べか物語』などとともに、山本周五郎の数少ない現代ものの1篇。物語の時は、戦後まだそれほどの年数を経ていない頃、とはいっても昭和30年代の前半あたりだろうか(朝日新聞の夕刊に連載されていたのは昭和37年4月から10月まで)。舞台は架空の場所だが、周五郎がかつて住んだ浦安あたりであろうか。物語は、その吹きだまりのような町の住人に順次スポットをあてて語ってゆく。形式とすれば、連作短篇の集積であり、個々の人物たちが織りなす全体像がそこに浮かび上がるという仕組みである。彼らは全員は、いわば極貧の状態にいる⇒2025/11/28
みも
225
戦後…昭和20年代後半~30年代前半あたりかと思われるが、その流暢且つリズミカルな語りは、江戸庶民を映した古典落語を思わせる。隙間時間でも楽しめる1篇30頁程度の短編15篇で、貧民街に逞しく生きる庶民の行動や思いを赤裸々に綴る。ペーソスとユーモアと少しの酷薄さを底流に、過剰なドラマ性を帯びない人情噺が展開される。「街」と言うより長屋を中心とした界隈の、極めて狭小なエリアでのコミュニティでの妬み・嫉み・憤怒・悲嘆・羨望…それらを吐き出しながら日銭で暮らす人々ではあるが、僕ら現代人との相似性をも映し出す秀作。2021/02/15
じいじ
91
久しぶりに読む山本周五郎の現代小説は、千葉浦安を舞台にした『青べか物語』の姉妹作。架空の「街」を舞台に生活するのは、その日その日を愚直に生きる人たち。山周さんが、厳しい眼差しで、温かくユーモアを交えて、15篇の連作で書き上げた力作です。ただ、今作の舞台である「街」の全体の風情は、陰気で昏い雰囲気です。書き手が大好きな山周なので、読み心地は同じでも、私的には明るい仕上がりの『青べか物語』の方が好きです。2023/08/20
天の川
62
昭和30年代前半、どぶ川の西側にその「街」はあった。定職を持たず、ギリギリの生活を送っている人々が暮らす「街」。極度の貧しさは明日の夢を持たせない。住民達は互いのことを噂し、こきおろすことはあれど、助け合うことはない。そんな余裕がどこにあるというのだ。冷徹な目で描き出される15編。漠然と山本周五郎=人情物と思っていたのが覆された。本を手に取ったきっかけのクドカンのドラマの人間模様の切なさや優しさよりずっとシビアな世界だった。「僕のワイフ」「親おもい」「プールのある家」がドラマと重なって心に残った。2024/05/07


![サキュバスは甘くて美味しい双子を餌にする[1話売り] story05 ××LaLa](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2114716.jpg)