- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
古来、観月と日本建築は深く結びついていた――。敗者のシンボルか? 滅びの美か? 研究着手から15年。桂離宮、銀閣寺、伏見城を中心に、秘められた数奇なドラマを読む。
目次
第1章 桂離宮―月を仕掛けた建築(桂の地と月 さまざまな観月への配慮 ほか)
第2章 観月と日本建築(義満・義政と世阿弥 幽玄美のルーツ・西行の月 ほか)
第3章 勝者と敗者のシンボル(桂離宮と東照宮 勝者の象徴と敗者の象徴 ほか)
第4章 伏見城―豊臣秀吉の死の不安(たび重なる身内の死と朝鮮出兵 月と狂気 ほか)
第5章 銀閣寺―足利義政の孤独、月への逃避(銀閣寺の紅葉が美しい理由 月への逃避 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
和草(にこぐさ)
12
月への想いが強かった時代。月を観る為に軒を短くしたり、櫓を建てる。今では考えられないほど月を意識し、見ていたのですね。2014/06/24
スズツキ
5
リフレッシュ感覚で頭を空にしてさらっと読もうとしてたが、思いのほか面白く結構考えながら読んでしまった。本筋とずれるが、銀閣についての記述が非常にインパクトがあった。そうか、そんな歴史があったのか……。2015/06/03
編集兼発行人
1
我国において月が建築へ及ぼした影響に関する考察。桂離宮伏見城銀閣寺といった有名な建造物を主な材料にしながら観月という目的が構造や意匠の中心的な主題に置かれた際の考え方と往時の状況とを平易な言葉で解説するという構成。中秋や春秋分など節目において最も美しく鑑賞できる方位に合わせて書院の向きを決定する程の配慮や政争での波乱から周囲への不信感が施主に齎す無常感により引き起こされる彼岸への指向などを垣間見るにつけ同様の権力に基づきながらも豪華絢爛で無節操な誇示とは対極の寂寥感と我儘加減とが皮肉にも表出されている感。2014/10/15
ビシャカナ
1
日本建築や日本美術に対する考え方や見方として面白い。月を幽玄やわびさび、未完の美や滅びの象徴として日本建築のみならず、和歌や宗教などを読み解く月に関する文化論でもある。しかし論理の飛躍に事実誤認や根拠薄弱が見られる。そしてどうにもネットで調べた限りでは専門である桂離宮に関する理論ですら疑問があるようだ。あくまでも数ある中の一つの考え、一つの物の見方として捉えておこう。一方で銀閣寺の章は義政の狂気を感じる読み物として秀逸。2014/04/06
ユウティ
0
ちょっと難しいっていうか眠たくなっちゃう部分もあったけど、面白かった。桂離宮も銀閣寺も西芳寺に倣っていたのか、知らなかった。前から行きたかったけど桂離宮と苔寺行きたいなぁ。知ってる漢字もなんと読んだらいいか分からないから、和歌にはふりがなをふって欲しいな。2015/06/12
-
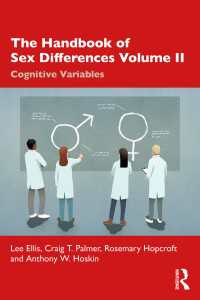
- 洋書電子書籍
- 性差ハンドブック(全4巻)第2巻:認知…







