- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
日本人はイランに対してどのようなイメージをもっているだろうか。革命、戦争、日本に大挙してやってきた労働者……。しかし、それはイランの「非日常」的な一面に過ぎない。古代に広大な帝国を築き、正倉院へガラス器をもたらしたペルシアは、アラブのイスラーム勢力や欧米諸国の侵入や干渉を受けながらも独自の文化を守り抜いた。不安定な世界情勢のなか、現在も模索を続ける人々の真実の姿を伝える。
目次
序章 イラン人の日常生活と文化
第1章 ペルシア帝国の栄光とイラン文化の形成
第2章 イラン文明のイスラームとの融合
第3章 西欧帝国主義との出会いと宗教社会
第4章 民族運動の台頭と挫折
第5章 イラン‐アメリカ相互不信の背景
第6章 イランの伝統文化の探求
第7章 模索するイランのイスラーム
終章 イランはどこへ向かうのか?―イスラームからイラン・ナショナリズムへ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こぽぞう☆
20
図書館本。中公新書の「物語〜〜の歴史」シリーズは、著者によって当たり外れが大きいが、これは良かった。アケメネス朝ペルシアから2002年までの通史だ。アケメネス朝時代に、ナイル川と紅海を結ぶ運河があったらしい。20世紀以降の歴史については、欧米の理不尽に同じアジア人として、めちゃくちゃ腹立った。2019/08/17
fseigojp
16
オスマン、イラン、ロシア、イスラーム諸国のことがわからんと おるふぁん・ぱむくの雪が読んでもなかなか。。。。2019/11/19
ピオリーヌ
11
全前七章のうち二章でサファヴィー朝終焉を扱うなど、近現代の比重が大きい。パフラヴィー朝〜イスラーム革命〜現代の記述は初めて知る内容も多くとても為になった。1940年代に首相として活躍したモサッデクが特に印象的。また、アケメネス朝、ササン朝からなる華やかな古代帝国を築き、イスラームによる侵略を受けつつも文化的特色を維持してきた点が現代イラン民族のナショナリズムに通じているとあり思わず膝を打った。2019/05/04
hitsuji023
9
イランの歴史がよくわかる。日本もイランも大国に翻弄されるという意味では同じような立場なのではないか。何より日本にとってイランは重要な石油の供給国である。本書でも「アメリカとの無用な軋轢は避けるべきだが、無批判な追従は、中東における日本のイメージを曇らせることになりかねない」とあるように上手くつきあってほしいものだと思う。余談だがロシアというのはどの歴史の本を読んでも約束を守らない国だし、アメリカは他国の政治に干渉する国だという感想を持った。2023/11/26
おらひらお
8
2002年初版。有史以来のイランの歴史を概観したものです。アケメネス朝、ササン朝などの古代帝国も紹介されていますが、多くのページは近代以降に費やされています。アメリカ人にもお勧めしたいですね。あと、イランでは政治的開放性があると政治や社会の混迷が起きる傾向があるそうです。2013/10/11
-
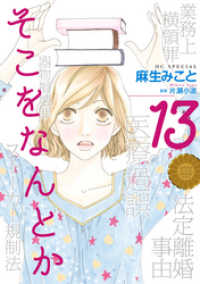
- 電子書籍
- そこをなんとか 13巻 花とゆめコミッ…
-
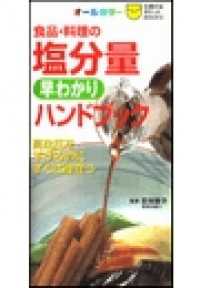
- 電子書籍
- 食品・料理の塩分量早わかりハンドブック…






