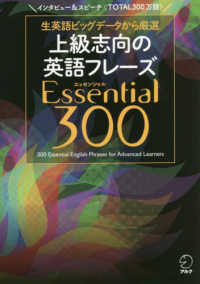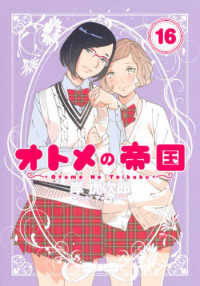- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
日進月歩で進化するデジタル・テクノロジー。インターネット、デジタル動画、携帯電話……1と0で構成される世界では、誰もが<著者・情報発信者>になり得る。<モノ>から飛び出した情報は一人歩きし、著作権はあいまいになり、本や写真の奥深い質感は失われていく……。昨日の世界が明日には激変する電脳社会において、時代のテンポに目を奪われる人間は何を喪失し、何を求めているのか。今日のコンピュータ理論を基礎づけた<哲学>の意義を問い直し、「デジタル時代」の現代を斬る異色の哲学書。(内容例)IT革命とは何だったのか/<モノ>から離れた情報は喜びを与えてくれるか/文章表現のカラオケ化/大学の権威は失墜するしかないのか/哲学にとって<現代>とは何か/「書物」の衰退と哲学<者>の権威/「環境にやさしい」に隠された「人間中心主義」/超強力版・人間機械論/クローンにみる「現代人の衰弱」/人間がコンピュータに負けた?
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
B.J.
5
●スピーカーとアンプのオーディオ世界、万年筆と原稿用紙の文字世界、カメラとフィルムの写 真世界など、従来、確固とした領域を形成してきた各ジャンルは、キーボードとディスプレイのなかに、あるいは手に握られた携帯電話の中に、溶けて崩れてしまっているのである。・・・本文より2020/03/19
Naota_t
3
★3.1/2000年前後の本は、大体がインターネットの危険性など負の側面(リスク)を危惧している。本書はそれを哲学の側面から述べた内容。写真家の藤原新也も「濃密な人間関係にリアリティを感じる旧世代と、淡白な感性のコンビニ世代の分離の問題」と捉えているし、ニーチェも「誰もが読むことができると言う事態は、長い目で見れば、書くことばかりか、考えることまでも腐敗させる」と言い切る。いつだってパラダイムシフト(変わること)は怖いものなのだ。AI技術が興隆する現代、哲学者たちは大いに議論のしがいがありそうだ。2023/06/21
暁人
3
臓器移植に関する話を調べるため読んでみた。脳死は人の死であり、それで助かる命があるなら臓器移植は積極的に行われるべき、というのが一般論だが、ことはそれほど単純な話ではないようだ。他者の死によって得た臓器は、体内では「異物」となり、拒否反応を引き起こす。移植者はその異物によって生存を許される、という根源的矛盾を抱えている。これは現代の科学全般が抱える問題ではないかとも言える。2013/08/01
青ポス
1
10年ほど前の本だが興味深かった。情報技術について哲学(主に認識論)から考察する。議論はおもしろいが、逆にページ不足で収まりきってない感じがした。一読すべき一冊。2013/03/13
さとう
1
わりと軽く読めた。でも、要点をきちんと書こうとすると記憶だけではちときつかった。 PCなどの「デジタルな」情報機器に習熟するとともに、バルナック型ライカや中世ヨーロッパの筆写本に凝り始める話がちょっと興味深かった2011/08/20
-

- 洋書電子書籍
- Meta Learning With …
-
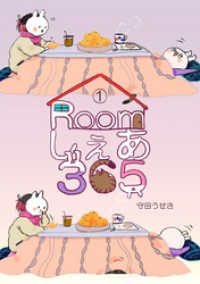
- 電子書籍
- Roomしぇあ365(1)