- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
計算は速いのに文章題になると意味をつかめない。英会話は得意なのに簡単なつづりの間違いを繰り返す……。知的には遅れがないのに、特定の学習に困難を示す子どもたちがいる。学習障害(LD)といわれる範疇にあるか、それに近い子どもたちである。通常の学級で学習している彼らへの効果的な支援のためには、本人だけでなく親や教師ら周囲も対象とするサポート体制を築くことが必要だ。新しい教育への取り組みを模索する。
目次
第1章 学習障害(LD)とは何か(定義と判断をめぐる問題 ニーズによって支援を決める ほか)
第2章 学ぶ側のニーズ(ディスクレパンシー 得意を伸ばしますか、それとも不得意を返上しますか ほか)
第3章 教える側にもあるニーズ(「これまでの子ども」とは違うの? 特別な指導法はあるのか ほか)
第4章 サポートシステムの構築(二〇一〇年の日本の小学校 「先生、一人で悩まないで」 ほか)
第5章 多様なニーズに応える教育と社会(ニーズを把握する習慣 サイエンスという視点 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
絵本専門士 おはなし会 芽ぶっく
8
娘に頼まれて借りました。大学の授業の参考にするそうです。内容だけちゃっかり聞き出す母(笑)2023/03/11
HedgeHogs
4
・相手が変わるのではなく自分が理解して変わっていく ・専門的な知識と研究、サイエンスとそれを実行する現場 ・学習障害という言葉を使うのなら、指導障害と言う言葉も使うべきだ ・ニーズの把握 ・チーム ・定義 ・レインマン ・原因把握 ・指導障害 ・楽しいと思うか思わないか ・研修、専門家 ・多様化2014/09/30
とーとろじい
3
著者が文科省等の政策に関わっているため、本書のテーマは教育機関におけるLDの支援であり、LDとは何かについての概説書ではないことは注意が必要だ。発達障害がクローズアップされて間もない時期の本で、アメリカの教育支援について紹介されている。個々人のニーズに対応すべしというのが著者の主張だが、学級人数の問題や過労問題があるなかで教員にその余裕があるのかは疑問である。特別支援学級の専門性という前提も怪しいものがあるが、教員への支援が必要なのは間違いない。成人後のLDの実情も気になるところである。2021/12/18
Nobu A
3
職場でも対応を求められるLD。しかし、自分自身がよく分かっていなかったので手に取った(2002年初版)図書館本を読了。1%強が特殊教育を受け、これから増加すると言われている。均質性から多様性への転換が迫られる日本教育界。しなやかな移行に教員の理解と対応や親や住民を含む地域社会のサポートが不可欠。「取り出し」ではなく「包み込み」が求められ、数十年前から取り組んでいるアメリカに学ぶことが多い。非常に重たい言葉である「学習障害」に適切な対応が出来ない「指導障害」の存在。耳が痛い話だが、正に目から鱗。日々勉強。2016/09/19
す
2
日本の教員は国際的に優秀だと聞くが、学習障害を含めた発達障害を持った生徒や児童への指導はアメリカに倣うところが多いように感じた。発達障害を持つ生徒・児童への指導を困難だが楽しいものだと考えるアメリカの教員が多いことが印象的だった。日本では、最近の傾向として、指導が困難な生徒・児童を重荷に感じ、命をたつ教員も多いため、ワクワクする壁だと思えるようになれば、教育の質もより向上するのではと思った。2014/10/09
-
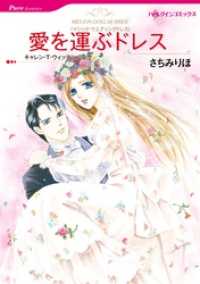
- 電子書籍
- 愛を運ぶドレス〈マジック・ウエディング…
-
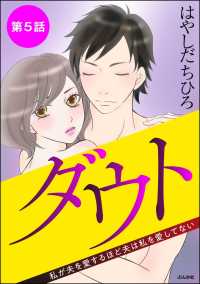
- 電子書籍
- ダウト 私が夫を愛するほど夫は私を愛し…
-
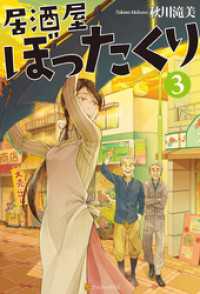
- 電子書籍
- 居酒屋ぼったくり3 アルファポリス
-
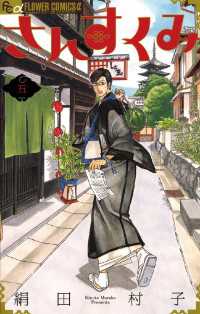
- 電子書籍
- さんすくみ(5) フラワーコミックスα
-

- 電子書籍
- コードギアス 双貌のオズ(3) 角川コ…




