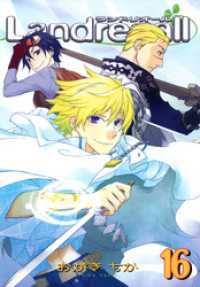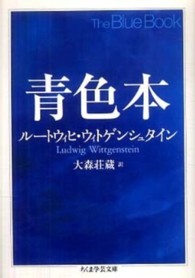- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
なぜ、私の前に世界は「現象」しているのか。この問いを巡り、現象学の祖はいかに思索し、どのような限界に漸近していたのか。気鋭の哲学者による驚きに満ちた「現象学」解読の、そしてフッサール超克の試み。(講談社選書メチエ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
K
13
「世界が現象する」とはどういうことなのか。フッサール現象学の本質が見えてくる良書であった。半年程フッサールに触れているが、だんだんとその内実が見えてきたように思う。現象学そのものも面白いのだけど、それに関連して自我論や時間論にも興味があるので、フッサールには、今後も付き合っていきたいと考えている。2021/12/28
またの名
13
「だって、こんなにも頭が悪く鈍重な人が、ニ十世紀を代表する哲学潮流のひとつである現象学の創始者であるというのだから、なんだか勇気が出てくる話ではないか」というのはもちろん好意から出た言葉。アイデアは面白いが突き抜けないフッサール哲学の乗り越えを多くの優れた現象学徒と同じくフッサール哲学を用いて、しかもフッサールの解説として実践。先入観を含む一切の判断を停止したのちに自我や現象が見出せる地点で、師の先を進んでさらにそれらを現象せしめる規定し得ない何ものかに迫る。結論に仏教的な感触があるけどそれはそれで良い。2016/12/09
hakootoko
5
『これが現象学だ』と構成は変わらないけど、フッサールを批判してみている。思ったのは読んだことないけど差延的な?とか思った。先に挙げた谷徹に比べて冗長的なので考えながら読むのに良いです。2021/07/02
グスタフ
5
斉藤氏は、フッサール師の思考を徹底することで、ついにはそれが成り立たなくなる地点にまでその思考を追い詰め、独自な境地を切り開くことを目指す。たぶん、ハイデガー、メルトポンティ、サルトルなども、その道を歩んだ人たちなのだろう。この本は、その師を、無味乾燥、鈍重、頭が悪い等々、これでもかというほど非難するところから書き始められる。フッサールは、この師なら易々と乗り越えられると、誤解させ、その気にさせる天才だったのかもしれない。フッサールは哲学史上ソクラテスと並ぶほどの優れた師だったのではないか。2012/10/13
ch
2
フッサール入門書ではあるが、フッサールの基本概念ではない「想像力」等を掘りさげて、「現象すること」の内実に迫り、フッサールの現象学とは違う立場に立つ。にもかかわらず、現象学の問題圏や核となるものが明確になり、入門書として成功しているように思える。ノエマーノエシスに対応した、「ありあり感」を表すものとしてのリアリティーアクチュアリティという述語はおもしろい(これは筆者ではなく木村敏氏の提唱によるらしいが)。そしてこれは、後期フッサールの重要概念である「顕在性」、「潜在性」あるいは「地平」へと繋がっている。2012/02/29