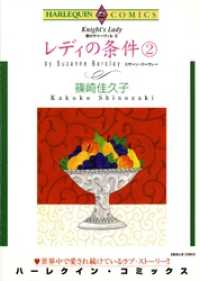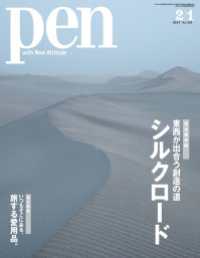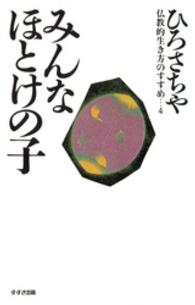内容説明
犯罪現場には血液や体液がさまざまな形で残されており、多くの捜査情報が得られる。科学警察研究所で血液、体液、DNAの鑑定に長年携わってきた女性鑑定官が語る事件の数々。
※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、予めご了承ください。試し読みファイルにより、ご購入前にお手持ちの端末での表示をご確認ください。
目次
プロローグ 初めての鑑定―科学警察研究所というところ
第1話 歩く血痕
第2話 Rホテル殺人事件
第3話 キメラ
第4話 親子鑑定
第5話 人獣鑑別
第6話 尿斑
第7話 流動血―強姦事件
第8話 性癖―DNA型鑑定の現在
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はる
12
図書館本。ふと書名が目にとまって借りてきたけれど、なんだかしっくりしないままに読み終える。ほんとうにあった事件はやはり妙に生々しい。(抗ヒトヘモグロビン沈降素以前の潜血検査!たいへん過ぎ。というより試薬が仕事しすぎ)2016/09/09
Humbaba
10
正しい分析結果を出したとしても、そこに持ち込まれていたものが誤っていれば鑑定結果に意味は無い。そのことを理解して、自分たちの仕事の範囲を認識する。何でもできるわけではなく制限があることを理解した上で、必要な情報を集める事こそが重要である。2015/05/28
naginuko
8
「真犯人はー」からこっちに来たのだが、肝心の足利事件についてはなにも語られていない。「DNA型鑑定はあくまで型を分類するもの、血液型の鑑定となんら変わらない。捜査を補佐する役割しか担えない。ここを間違えると、いつかとんでもないことが起こる…」というのが精一杯の自己弁護か。自身の鑑定結果が17年もの冤罪を生んだことに関してはどう思っているのだろうか。この本を上梓したのは2001年。まだ再審請求の道は開いていなかったが、言い訳がましいことを書いてあるのは、正確性に疑いがあることがわかっていたからではないのか。2015/05/03
あられ
7
『殺人犯はそこにいる』に出てきた本。「被疑者が犯人であるか否かは、鑑定官が言及することではないのだ。」との一文を見つけたが。全体を見渡すと、こんな事件も、あんな事件も、鑑定で解決しました、と自慢気。間違ってはならない鑑定で、間違ったことは全くなかったような書きぶりだが、間違ったこともあったと、認めてほしいところだが、世界がひっくり返りでもしなければ認めないのだろう。子育てについては、同感する部分があったが、出版当時も、いまはさらに、子連れで行けるような牧歌的な職場は皆無だろう。2014/03/16
ポルポ・ウィズ・バナナ
7
「殺人犯はそこにいる」中、結果の怪しいDNA型鑑定に携わった科警研S女史の本。科警研の独立性、鑑定の不正確性等を記しているが「ゆうてることとやってることがちゃいますやん」という印象が拭えない。ゆえに、例えば熟練鑑識のアクロバティックな鑑識結果などは「ほんとかよ?」と感じてしまう。本篇とは関係ない部分で日本における親子鑑定・養子縁組問題は大変納得しました。つまらん感想書くとS女史“も”個人の資質としては真っ当な方なんだろうが、それを許さない警察組織(というか日本型組織)の問題が大きいんだろうな。2014/02/08