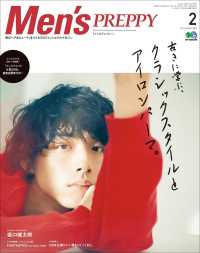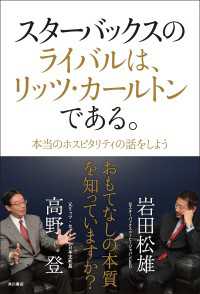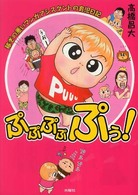内容説明
〈桜桃忌〉に出られなかった事から太宰治を回想する「玉川上水」、敗戦直後郷里に疎開した頃の日常を描き飄逸味を漂わせた「耳かき抄」。表題作をはじめ「逢びき」「下駄の腰掛」「山つつじ」「川風」「柚子」「御水取」など身辺の事柄を捉えて庶民のうら哀しくも善良でしたたかな生き方を綴った諧謔とペーソス溢れる木山文学の真骨頂、私小説的作品を中心に新編集した傑作11篇。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たくろうそっくりおじさん・寺
65
近頃、テレビもあまり観ないで木山捷平の本ばかり読んでいる。じきに飽きるだろうとは思うが、飽きるまでに木山捷平を大好きな存在に育てておきたい。本書はユーモア小説選という事で、肩の凝らない短編集である。本当に「東海林さだおの文章か?」と思うくらい東海林さだおが木山捷平の影響を強く受けているのがよくわかる。解説の坪内祐三が言う通り、「テーマが無い」ものばかりである。今風に言えばメッセージ性が無いというか。しかし独特の表現や渋いギャグセンス、切り上げ方が意外なものもあって笑わせられながら心奪われる。これもお薦め。2019/08/08
軍縮地球市民shinshin
12
「ユーモア小説」とあるが別に読者を笑わそうとしている小説ではない。あくまで木山の私小説である。日常の瑣事が書かれているが、本書に収録されている短編には、若い女性との邂逅の話が多い。最後の「御水取」などはコトに及んでいるのだ。だからといって木山の文章がいやらしいわけではなく、あくまでサラッと読めてしまう。性的な話でも、ソ連軍の満州侵攻の話でもサラッとしているのだ。そういうのを「ユーモア」と呼ぶのだろうか。割高な、だけど文学好きな人が読者である講談社文芸文庫にはぴったりの作家だといえる。2017/04/02
月
12
★★★☆☆(尾崎一雄の小説で木山捷平の名を見つけ今回手を伸ばす。この人も個人的に名は知れど作品は知らずの作家。しかも、阿佐ヶ谷文士だったのかと初めて知り、何やらまた太宰や井伏さん周辺へと近づいて来る。太宰の玉川上水も収録。全篇を通して、独得の軽い(軽妙な)文体は今の時代読んでも違和感なく伝わるというか、寧ろこの時代にこの文体は別の意味の個性であったのではないだろうか。中には過酷な経験もある中で、ある意味飄然とし、時にユーモアさえ交える。独特の世界観を彷徨う 木山捷平の世界がここにある。) 2012/11/05
きりぱい
8
飄々としているおじさんだなあ。私小説だからそれは著者でもあるのだろうけれど、何というか他愛ないゆるさでまじめに不埒というか、こんなこと言ったらあれだけれど、いまいちぱっとしないぬけた感じに哀愁の背中を感じる。日常の奥様とのやりとりや、女性との出会い、戦後の話など、ドラマチックだったり、苦労があったりしたはずなのに、どれもまったりと妙にぬくもりもあって、可笑しさの残る話になっている。表題作、「コレラ船」「下駄の腰掛」「柚子」がいい。2014/08/13
YO)))
7
ユーモア小説,と呼んでしまうと漏れてしまうものがある.控えめでなくかといって押付けがましくもない絶妙の諧謔味,それは人生の悲哀や死というものを見つめる目によって,丹念に(或いは時に冷酷に)裏漉しされたものではないだろうか. 太宰の最期のその前後の回想,「玉川上水」,「逢いびき」のノー・ズロの話辺りが好み.2014/03/07