- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
日本企業は二度の石油ショック、ニクソン・ショック、円高などを克服し、強い競争力を作り上げてきた。日本企業に比較優位をもたらしたのは組織的知識構造をコアとする労働スタイルにあった。それは個別的な直感=暗黙知を形式知化して組織全体のものにし、製品やサービス、業務システムに具体化していく組織の運動能力をさす。いくつもの優良企業のケーススタディをもとに知識創造と知識資産活用の能力を軸として、大転換を迫られている日本的経営の未来を探る。
目次
第1章 情報から知識へ
第2章 21世紀の経営革命
第3章 第五の経営資源
第4章 「場」をデザインする
第5章 成長戦略エンジン
第6章 創造パラダイムの経営
-

- 電子書籍
- その手をつないで眠ろう【タテヨミ】第9…
-

- 電子書籍
- 毒女、誤って王太子をオトす(単話版9)…
-
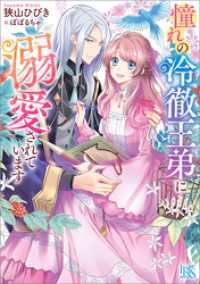
- 電子書籍
- 憧れの冷徹王弟に溺愛されています【特典…
-
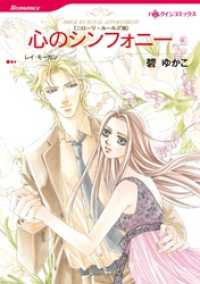
- 電子書籍
- 心のシンフォニー〈ニローリ・ルールズⅦ…
-
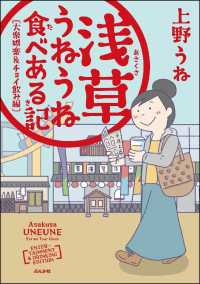
- 電子書籍
- 浅草うねうね食べある記 大衆娯楽&チョ…



