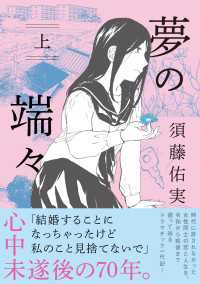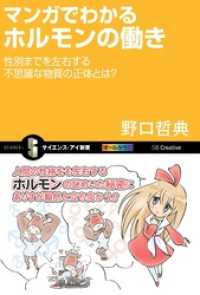内容説明
【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。
私たちになじみの深い将棋はいつごろどこで発明され、どのような道をたどって日本に伝わったのか? 九段の棋士である著者がソウル、台北、香港、バンコク、ニューデリーとたどる紀行。現地の棋士との対決も見もの。
※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字サイズだけを拡大・縮小することはできませんので、予めご了承ください。 試し読みファイルにより、ご購入前にお手持ちの端末での表示をご確認ください。
目次
日本篇―兵どもが夢の跡に残された駒の謎
タイ篇(バンコクの名人たちとの熱い闘い マーク・ルックの起源はチャトランガか)
中国篇(中国の象は河を渡れない 二千五百年前?象牙の駒との邂逅)
韓国篇(韓国の象は「用」の字に歩く 百済人が伝えた?日本の将棋)
インド・スリランカ篇(マハラジャの遊びシャトランジ 妻にチェスで負けたシヴァ神 インドから発した東西のチェス・ロード)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
そり
9
将棋のルーツを探る海外旅行記。大陸から伝来してきた将棋が形態を変えてゆき、現代のルールに収まる頃は鎌倉幕府の時代と見られる。その時代ではまだ「二君にまみえず」という考えは一般的でなかった。だから「駒の再使用」という日本将棋独自のルールが、人々に不自然なく受け入れられた。なるほど。一目やってみたいと思ったのは中国将棋で、なんと盤の真ん中に河がある。韓国将棋の、一部の駒の配置を自由にしてよいというルールも興味深い。これを応用すれば勝手にルールを作って、力戦調にする楽しみ方もできそうだ。2013/06/06
Gamemaker_K
5
世界の将棋型ゲームの世界に引きずり込まれるきっかけとなった一冊である。古本屋で購入後、何度も何度も読み返している。世界の将棋に触れる旅の旅行記として、これ以上ない名著だね。…個人的に将棋のルーツは解き明かされない方がよいのではないかと思う。多分、シャンチーかチェスかやり飽きた奈良平安あたりの一般人が、取った駒使ってみたら面白かった、とかそんなのが始まりだったんじゃないのかなーなんて考えているので。2019/02/04
kokada_jnet
3
日本将棋の東南アジア~中国江南由来説を説いた、有名な本。この内容を批判的に紹介した本を何冊も読んでいたので。すっかり既読のつもりになっていたが。あらためて読んでみたら面白い。あちらこちらで、現地の将棋を指す大内先生がアツイ。朝鮮象棋って、中国象棋と同じ駒・配置なのに、こんなにゲーム性が違うものなのか。2013/11/07
naoto
0
将棋の本であって、将棋の本でない。この本を読んでも、将棋は強くならない。将棋のルーツを探す、旅本。韓国、中国、タイ、インド、スリランカ。将棋に「持ち駒制」があるのは、駒の形にあり。なるほど。こういう「文化の世界史」、もっと読んでみたい。2014/08/07