内容説明
江戸前鮨が今のような姿を取り始めたのはいつ頃のことなのか? 大阪と江戸前の鮨の違いは? すし屋でのマナーとは? 私たちの風土と文化が育てた日本人のもっとも愛す鮨の素顔に迫る一冊。すし業界に長く関わってきた著者ならではの視点で鮨の歴史と食文化を辿る。『小僧の神様』の屋台の鮨から現在のあの名店の握り鮨まで、食べて美味しく読んで楽しいすしの世界と歴史。元来、庶民の食べ物であったすしの魅力を、その誕生に遡りながら、なぜすしが人々に愛されてやまないかを豊富な写真を交えながら解説した。
目次
すしの歴史のあらまし
鮨・鮓・スシ・すし
空飛ぶドジョウのすし
江戸前ずし黎明期の二大有名すし屋
内店と屋台店
もう一枚あったスシの錦絵
橋のたもとの屋台の店
「か・べ・す」のすしの話
江戸前とはなにか
江戸っ子だってねえ、すし食いねえ〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
39
元本は1996年刊。著者は『すしの雑誌』主宰者で1926年生まれ。鮨業界の裏話が面白い。江戸の鮨屋には当初、店舗を構えて出前をする内店と、立ち食いの屋台があった。内店は仕事をした高い鮨、屋台は生魚の安い鮨だったが、生魚の鮨が人気となり内店が屋台を取り込んだと言う。明治の芝居小屋の鮨は箸ではなく長楊枝付き。固く握った濃い味付けの鮨は、醤油いらずで観劇向き。注目は、終戦直後に江戸前鮨を全国化した委託加工制度の話。配給制下で安く主食を提供する心意気と、浸透までの大変な努力。老齢の関係者への取材には執念を感じた。2022/05/18
lilysX
2
すしから広がる知らない世界2016/02/06
-

- 電子書籍
- 音羽マリアの異次元透視(分冊版) 【第…
-
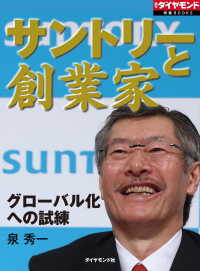
- 電子書籍
- サントリーと創業家 週刊ダイヤモンド …
-
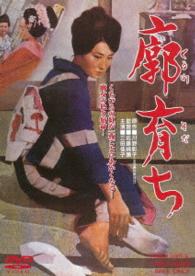
- DVD
- 廓育ち
-
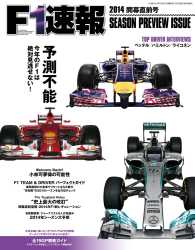
- 電子書籍
- F1速報 2014 開幕直前号 F1速報
-
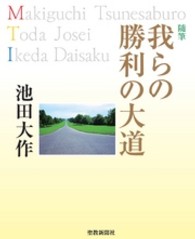
- 電子書籍
- 我らの勝利の大道 - 随筆




