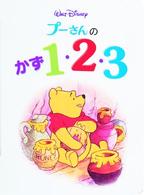内容説明
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、旧ソ連、パレスチナ……今なお世界を揺るがし続ける民族紛争はなぜ起こるのか、その実態はどのようなものなのか。著者専門のイスラム史と国際関係史を軸に、人類永遠の課題・民族問題の理解と解決のための基礎的分析を試みた意欲作。
目次
第1章 民族と国民
第2章 民族と知識人
第3章 ナショナリズムの歴史
第4章 多民族国家と帝国
第5章 民族と宗教
第6章 民族と経済と社会主義
第7章 人工移動と難民
第8章 移民と外国人
第9章 民族と多文化主義
第10章 民族の差異と平等
終章 「民族関係論」に向けて
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かわうそ
31
『「民族」に代わって「地域」を前面に打ち出して「地域自決権」を提唱する向きもある。』民族という概念が膨張するのを抑えるために地域を持ち出すのは無駄というものだろう。そもそも民族は地域と結びつきが強いのであり、民族によって地域は利用されるのもしばしばある。よって、民族と地域を切り離すことは不可能である。民族自決を自治権に置き換えるというのも中国を見れば失敗していることは明らか。人は物事を自分で決めたいという根本欲求があるので、自治が自治で収まりきらず自決になるのを歴史は証明している。2022/02/01
かわうそ
30
「他方、国民国家は民族自決や統治形態の民主的装いにもかかわらず、自国内に住む民族の多様性に寛容でないことも珍しくない。しかも、多数の民族が住む現実を隠そうとするばかりから民族の相違を無視しながら「一つの国民」としてただ一つの言語を用いた一つの法体系に服することを求める。むしろ、多民族国家では寛大に扱われた宗教の違いも、ここでは見過ごされないという逆説さえ生まれる」オスマン帝国が他の近代国家と比べて民族や宗教に寛容だったのも頷ける。 2022/01/30
非日常口
28
近代国家と民族、前近代の宗教、しかし人間のネットワークはポストモダンである現代は複合的な価値観が混在しているのが現代だ。佐藤優さんが「第三次世界大戦」について対談していた山内昌之氏が911以前に出版した本書は、我々が今結果として見ているEUやソ連崩壊の状況がまだ動的な時の感覚で描かれている。その中で、当時民族を考える上で使われたナショナリズム5分類、領土的自治と文化的自治などのカテゴリーや、過去が現代に巻き込まれる歴史解釈の問題、「われわれ意識」、民族紛争の責任の所在等に概括的かつ要点を抑え提示する。2016/01/13
masabi
14
民族とはなにか、という問いに始まりナショナリズムや民族紛争の事例が多く紹介されている。帝国は多民族を統治したために民族や宗教に対し寛容だったが、国民国家は国民の大多数が単一民族であり、他の民族や宗教に排他的、同化を迫り易い。今日のグローバル化を受け帝国の統治原理が再検討される。民族で差をつけるのではなく教育や習俗、生活様式を尊重する文化自治を推進する。領土・民族を単位とする意識ではなくどの文化が共有されているかが健全なナショナリズムや民族紛争を解決することに資する。経済的、政治的格差の是正も必要である。2015/06/23
ミッキー・ダック
11
1994年刊行。20年前に書かれた本だが、今なお世界で火を吹いている民族紛争を理解し考えるための幅広い視野と鋭い視点を与えてくれる。著者が言うように、少数民族が多数民族の価値に強制的に同化させられることなく個別の価値を私的に保持する自由を認めつつ、公的には超民族的な普遍的理念を共有することで民族・人種差別をなくし、民族間の経済的・社会的な格差のない世界を目指したい。そのためには、民族間の交流と話し合い、国連の平和維持活動が不可欠であるとしているが、現実は依然厳しく、政治家や知識人の責任と期待は大きい。 2014/09/23