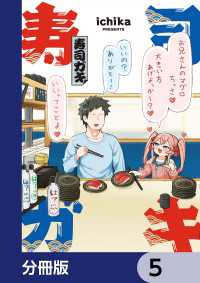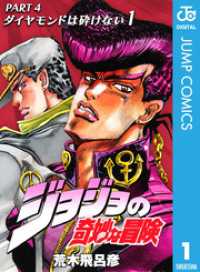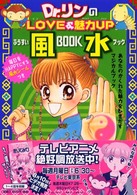内容説明
その日、日本中がテレビに釘付けになった。催涙ガス弾と放水にけむる安田講堂の時計台、顔をタオルで覆い、ヘルメットを被った学生たちが屋上から投げ下ろす人頭大の石塊、火炎ビンに灼かれた機動隊員の苦痛に歪む顔……その時、作家・三島由紀夫から緊急電話が! 時は「あさま山荘」事件の起こる3年前、昭和44年1月だ。全国民が注視した東大安田講堂の攻防戦に、警視庁の警備第一課長として臨んだ著者が、当時のメモを元につづった迫真のドキュメント。文藝春秋読者賞受賞作品。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶ~よん
80
東大安田講堂の攻防戦に、警視庁の警備第一課長として臨んだ著者が、当時のメモを元につづった迫真のドキュメント。当時の学生達のモチベーションは分からないし、勿論褒められた行動でもないのだけど、我々の時代や現代に比べて圧倒的な活気があったことが書面を通して伝わって来る。警察も学生も本気でやり合い、日本国民が中継に釘付けになった時代。催涙ガス弾、放水、火炎瓶。こんな時代が、日本にもあったのかと想像すら出来ない。我々は平和とコンプライアンスを手に入れ、エネルギーを失ってしまった。警察、学生、両者からそう思わされた。2025/10/07
Willie the Wildcat
19
学園紛争。問われたのは教育者、指導者のあり方。肝の据わり方もあるが、信念の有無という気がする。故に、東大・林文学部長。流石に、学生も認めざるをえない人物。印象深いのが、現場機動隊員。1つ1つのエピソード。隊員である前に、皆1人の人間。1970年日米安保条約自動延長後に、600名の機動隊員が退職。それまではほぼ”0”。責任感のみ!敬意。一方、警察内部、消防関係者、大学関係者・・・。組織の”壁”と官僚主義は、今も昔も同じ。嗚呼嘆かわしい・・・。2013/10/31
Chikabono
14
生まれる前の出来事、時々TVでやる安田講堂事件の記録。筆者が警察側の当事者とういことで貴重な歴史の記録だと思う。あくまで警察、機動隊側からの記録、意見にはなるが。2019/12/13
takam
14
60~70年代の日本は武力に対してアレルギーが強く、そしてベトナム戦争、革命の空気、精神的支柱の喪失により、日本人の学生たちが連帯を求めた時代だったのだろう。佐々さんもそう指摘している通り、大学受験で失われた連帯を作り上げるために反体制運動をやっていたのだろう。対照的に機動隊は金や名誉よりもゲマインシャフト的な文化を持つ組織で、大学生くらいの年齢でも反体制派を生け捕りにすることを使命として対応に当たる。学生達に非があるのかというとそうではなく、大学の運営者達も他人事で権威主義なところで信用がなかった。2019/08/29
モリータ
14
◆機動隊の"参謀"として"安田城攻め"が象徴する東大紛争(東大封鎖解除・神田カルチェラタン闘争規制)を指揮した警備一課長による回想。◆事実だけを追うならば、誤った印象を増幅しかねない「""」つきの比喩や、デフォルメと取捨選択のきつそうなエピソード(特に警察組織外の噂話)を割り引いて読むのは当然のこととして、1930年生(当時38歳)の著者が軍隊や戦国時代の用語を頻用して機動隊の「戦争」を語ることの意味は、次のような学生側に関する分析と合わせて考えるべき?2019/08/13