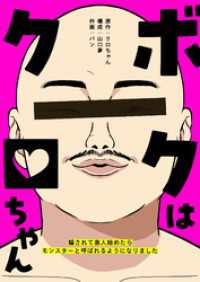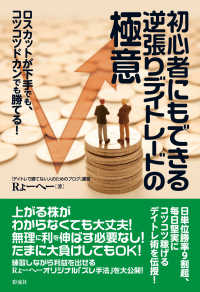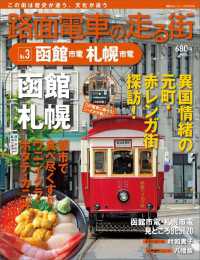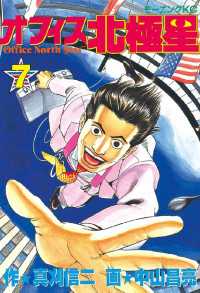- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
貨幣を経済学の封じこめから解き放ち、人間の根源的なあり方の条件から光をあてて考察する貨幣の社会哲学。貨幣を人間関係の結晶化と見て、自由と秩序をつくりだす媒介者としての重要性を説く。貨幣なき空間は死とカオスと暴力の世界に変貌するからだ。貨幣への新たな視線を獲得することを学ぶための必読の書。
目次
第1章 貨幣と死の表象
第2章 関係の結晶化―ジンメルの『貨幣の哲学』
第3章 貨幣と犠牲―ゲーテの『親和力』
第4章 ほんものとにせもの―ジッドの『贋金つくり』
第5章 文字と貨幣
エピローグ―人間にとって貨幣とは何か
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
70
この本は経済学的な貨幣論ではなく、社会学的あるいは文化人類学的な観点から貨幣というものがどのような役割を果たしてきたかを俯瞰している本です。ですので一般的な経済書とは異なった社会学的分野の本で、ジッドの「贋金つくり」などを分析していて貨幣小説として読むのではなく、経済学批判の書として位置付けたりして面白い見方をされています。2015/08/14
k5
63
タイトルは「媒介とは何か」がよかったんじゃないか、というくらい、主役としての貨幣の影は薄いです。貨幣は関係の制度化した媒介者として、法や倫理と同じ役割を持ち、貨幣の廃止を目指した社会主義が、それをあまりに経済的な存在としてみなしたが為に、秩序の崩壊を招いた、というのが、本書の書かれた1994年時点の問題意識なのだろうなあ、とぼんやりとは分かるものの、でも貨幣をテーマにしない方が面白かったんじゃないかと予感します。貨幣って魅力的すぎて描くのが難しいのかな。とても刺激に満ちた本で、もう一度読もうか迷い中です。2020/08/06
月をみるもの
18
まず ”貨幣と比較されるべきものは、言語ではなくて、むしろ文字である。文字と貨幣との関係をとおして間接的に、貨幣と言語とは関係づけられるだろう。 なぜ貨幣と文字との関係をいうかといえば、後で詳論するように、文字という存在が死と密接不可分であるからだ。死の問題をとおして、貨幣と文字は直接的に通じあう”。 そして "墓は素材的な意味での貨幣ではないが、死者と生者との交換の貨幣形式である"。 ということで、文字〜貨幣〜墓は、その本質(死を前提とした人間間の媒介物)を同じくする。 らしい。2021/03/06
ハチアカデミー
16
貨幣は死の観念を内包するとは何の謂ぞ! 読み始めはそのロジックが掴みにくかったが、本書を閉じた今は腑に落ちている。つまり、生とは流動であり変化であるのに対し、死は固定であり定着である。貨幣は他者との交易の道具であるため、一度貨幣による交換が成り立ったとき、その関係性、物と物との距離が固定化される。それは商品価値のみならず、曖昧模糊とした人間関係も、何を美とするかわからない芸術さえも、貨幣によって価値付けがされたとたん、定着してしまう。対象との距離を掴む基準が貨幣なのだ。貨幣を題材にした壮大な社会哲学!2013/07/11
Ex libris 毒餃子
12
死の概念を有するのは人間だけで、それ故に貨幣が生まれた、というぶっ飛び理論ですが、最終的には納得します。2021/05/16