- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
近代国家を担う立法・司法・行政三権のうちでも行政は政治の中枢に位置する。とりわけ日本においては、追いつき型近代化を遂行する過程で行政の果たしてきた役割は大きかった。しかし明治以来の国家目標が達成され、自民党単独政権が崩壊した今日、行政もまた変革を迫られている。即ち、各省間の競争エネルギーを駆り立てた最大動員システムはセクショナリズムの弊害を露呈しているのである。新しいシステムはいかにあるべきか。
目次
第1章 最大動員のシステム(日本行政の沿革 中央行政システム)
第2章 公務員制度と人事行政(高級官僚集団の管理 省庁人事管理)
第3章 最大動員の行政管理(予算編成―機能の連結 決定構造と調整 組織設計と組織管理 省庁内の最大動員)
第4章 トップと官僚(弱体な日本のトップ・ストラクチュア 日米トップの比較)
第5章 行政活動の変容(戦後行政活動の原型 行政の変容 国際化のインパクト)
第6章 中央地方関係(第一型自治 中央地方関係における均衡状態 第二型自治の提案)
第7章 政治的環境の変化と行政(行政官僚制と政党 官僚の自律性の困難 行政と利益集団)
第8章 行政変革の推進(トップの強化と戦略部門の設置 政策評価基準の変更と監査制度)
第9章 市民
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やす
2
日本の行政の歴史について。2024/12/01
壕野一廻
1
日本の行政とはどのようなものか。どのようになるべきか。バブル崩壊直後に書かれた本書は、日本的組織の職責があいまいなあり方を必ずしも誤りとしていないのが面白い。筆者はこれを最大動員のシステムと名付けていて、限られたリソースを最大限効率的に分配する仕組みだとする。人数は少なく管轄は広い日本の役所には適合的だったというのは説得力ある。 本書で提言されている縦割り打破と政治主導の行政改革という方向性はおおむね実際に行われたものの方向性と一致するように思うけど……。2020/12/22
daydreamer
1
今読むと古く感じるところもあるが、94年当時とどこが変わっていないか、というところが重要なところであろう。行革や組織再編等がなされた今もなお、行政の最大動員システムという村松の提示したものは変わっていないように思われる。総合調整、というのも未だ達成されていない課題ということになるのだろうか。政治と行政、官僚についての最新の議論にも目を通したくなった。2018/01/07
日の光と暁の藍
1
本書において村松氏は、日本の行政システムを最大動員という言葉で表現する。「最大動員とは、行政に利用できるリソースに関してできるだけ能率的に使用することをいう」(Pⅷ)。日本の行政が、非常に少ないリソースを用いて機能を果たしてきたことが本書で述べられている。日本は行政が大きすぎるとか、中央が地方に対して強い権限を持っているなどと世間やマスコミで言われるが、それらがいかに誤りであるかが本書を読むと分かる。人によっては難解かもしれないが、何度も読み返すに値する内容だと、自信を持ってお薦めする。2013/09/23
アブストラ
1
この方面の知識が無い私にはほぼチンプンカンプンでした。なにせ官庁の組織図もないのだ、この本は。西洋に追いつくための官僚制が今では逆機能を起こしている、政治のリーダーシップの強化、司法の活用が必要といった大筋のメッセージは理解した。実際、この本で提言された方向に過去二十年進んで来たような気がする。日本の地方は収入も支出も他国の地方と比べてケタ違いに大きいということは初めて知った。日本は中央集権だから地方に分権しろとマスコミにしょっちゅう聞かされているのだが。2013/11/05
-

- 電子書籍
- 素材の旨味を引き出す 塩とこしょうのシ…
-

- 電子書籍
- イリヤッド~入矢堂見聞録(10) ビッ…
-

- 電子書籍
- 嘘はやめよう
-

- 電子書籍
- ーヒトガタナー(7) 月刊コミックブレ…
-
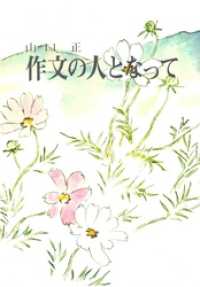
- 電子書籍
- 作文の人となって




