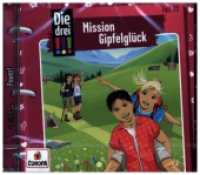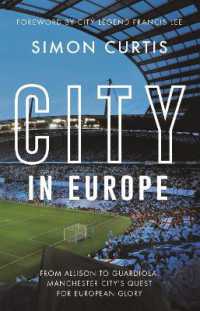内容説明
著者に「民話」を託したそれぞれの語り手の、厳しくも豊かな生のおもしろさ。果てしない知性を宿した「忘れられない日本人」たちの、生きた姿を伝える。
目次
第1章 佐藤とよいさん―戸数十四戸の山奥の村に生きる
第2章 小松仁三郎さん―おらは義務教育には参加しません
第3章 楳原村男さん―ガダルカナル島へ行かず憲兵学校へまわされて
第4章 佐藤玲子さん―最愛の夫を失って甦った民話の語り
第5章 佐々木健さん―神子職を奪われた祖母が語った民話の数々
第6章 佐々木トモさん―友はみな貸されて(売られて)いった村に生きて
第7章 伊藤正子さん―母の語りに育まれて
第8章 永浦誠喜さん―生涯を農民として生き抜く
最終話にかえて 商人の妻
著者等紹介
小野和子[オノカズコ]
1934年岐阜県生まれ、1969年から、宮城県を中心に東北の村々へ民話を求めて訪ね歩く民話採訪、民話の編纂に従事する。その傍ら、児童文学作品の翻訳や児童書の執筆も手がける。1975年に「みやぎ民話の会」を設立し、2005年まで代表、現在は顧問を務める。1995年に「みやぎ児童文化おてんとさん賞」、2013年に「宮城県芸術選奨」受賞。著書『あいたくてききたくて旅にでる』(PUMPQUAKES’2019年)で、2020年に「第七回鉄犬ヘテロトピア文学賞」及び、二〇二〇年に「第十回梅棹忠夫・山と探検文学賞」受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あじ
17
肩書を持たない3児の母が、民話の採訪者になり半世紀。宮城を中心に足繁く数十年通い、語り部との絆を撚り合わせた本書は、令和の「忘れられた日本人」だ。“忘れられない日本人”とした所以は、頁を重ねるほど由縁であることに紐付けされていく。戦前、戦中、戦後の貧困に苦しめられた農村の暮らしを背景に、語り部の人生が民話とタイアップされクローズアップされる。「語られる民話は、人を選んでその身体に入り込み、そこで生き続けているかのように、わたしには思われるのです」著者の言葉が沁みる。語り部の泣き笑いが忘れがたい名著だ。2025/02/01
チェアー
6
どの語り手も民話を殊更に伝えようとは思ってこなかった。だが、そういうものの中にこそ、地域の小さな歴史が込められていて、なくしてはいけないものなのだとわかる。大きな言葉で書かれた歴史は、小さな小さな家族、個人の歴史の積み重なりでしかない。そして、歴史のエッセンスが民話として伝わっているのだ。 そして今や小野さんが民話の語り手となって私たちに伝えてくれている。 2024/05/10
naok1118
2
小野和子の民話採集の過程を民話語り者との対峙の中から、語るものと聞く者のそれぞれの心情や心持を中心に、それこそ語るように記録する。とても心地良い語りを聞いているような読後感がとても良い。前作も良かったけど、これも素晴らしい。2024/09/23
HISA
2
☆☆☆☆☆宝物のような素晴らしい本でした。小野和子さんが、民話とその語り手に敬意を払い、真摯に向き合ってきたからこそ、沢山の貴重なお話を書き記せたのですね。民話は、知っている方が亡くなると消えてしまう本当に大切な文化遺産だと思いました。しかし、昔の人は戦争も含め大変な経験をして、生活の知恵を持ち、なんて豊かなんだろう、私は薄っぺらいなと感じずにはいられませんでした。2024/07/15
Teppei Sakano
2
民話とはその語り手その人を含めた物語であることが切々と感じることができた。そしてその物語を受け止める聞き手が民話というバトンを受け取ることで、道徳、文化、思想、生活の知恵を受け継いできたんだろうな。聞き手はそれをただの記憶上の物語ではなく、先達の語り手の精神も含めた民話として自身の中で「醸し」、切れば血の出る自分の言葉になったときに、新たな語り手として語りはじめるようになったんだろう。2024/04/24