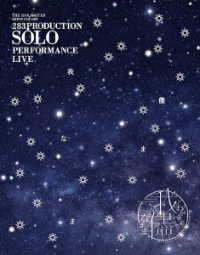内容説明
縄文時代の土器づくりを追いかける「土から土器ができるまで」と、実際に土製品を作る「小さな土製品を作る」。この二つの土器づくり読本を一冊にまとめました。Side A「土から土器ができるまで」世界遺産である「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産である是川石器時代遺跡の収蔵展示施設「是川縄文館」の協力のもと、縄文文化の根幹を担っていた土器づくりを追いかけ、土器や土偶や土製品がどうやって作られているかをドキュメント。粘土を山から採取し、形作り、乾燥し、焼き、黒くする。Side B「小さな土製品を作る」実際に個人でも作れる小さな土製品を作る方法。さらには現代人はどんな土器や土偶や土製品を作るべきかの考察と、造形家山内崇嗣さんのかわいい土製品の紹介。それに加えて実際に青森県八戸市の中高生たちに作ってもらった土製品のワークショップの様子と作品の紹介。
著者等紹介
山内崇嗣[ヤマウチタカシ]
石川県生まれ。1998年武蔵野美術大学油絵学科卒業。国立市消防団参加経験あり(2012‐2017)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やま
12
「縄文人に相談だ」の筆者が縄文土器の作成に挑戦しています。縄文の技を再現しながら、かつ、現代風にアレンジもするという遊び心も盛り込んでいます。野焼きはハードルが高いが、こんな簡易な焼き方もあったとは。驚きです。土器編と土製品編(土偶など)の2本立て。2022/11/03
あゆぷ
4
右と左と両側で独立した内容で、一冊で二度楽しめる本。『土から土器ができるまで』はもうNHKでドラマ作ればいいと思うくらい(私の中で)盛り上がった。焼き上げの現場に行きたかった。いつか、行こう。『小さな土製品を作る』の方は、軽い読み物として進めていたら、ワークショップのところで現実の厳しさを見せつけられた。殆どが焼成せずに崩れてしまったということか。土偶は体の一部を壊した状態で棄てられていた、と本で読んだことがあったけれど、実際に当時もいっぱい壊れて已む無く棄てていたのかもしれない。2022/12/20
Go Extreme
4
土から土器ができるまで: 土を探す 粘土を作る 成形 乾燥 焼成 炭化焼成 小さな土製品を作る: 小さな土製品を作るその前に 小さな土製品を作るっていうけれど じゅじゅつについて もっと暮らしの呪術 ヤマウチ式土製品の作り方 粘土・成形・焼成・完成・片付け みんなの小さな土製品2022/07/05
mamaou
2
これは!左右どちら側も表紙で2つのテーマで分かれているじゃないか〜。縦書き横書きどっちも日常的にアリ!の日本語ならではの製本にまず感動。そして勿論内容も端的でわかりやすく無駄が無く、更に更にとっても美しい写真満載。なんとなく好きだった土器がとても好き!に変わりました。さすがに一人きりで個人で焼くのは無理そうなのでワークショップあったら絶対参加しなくては!2023/01/15
海冨長秀
2
昔は、伝統的な暮らしを劣ったものと見る偏見があったのだけれど、とんでもない。私が土器作りを一から始めたら絶対作れない。土選び、相応しい土の選び方、焼き方、私では絶対思いつかないような方法・工夫があり、数々のトライ&エラーの繰り返しでノウハウを縄文人が積み上げていったのだということを勝手に想像し、一人感動し震えました。本格的な土器は、なかなか場所等で、困難なため、一人で出来る簡易な土器作品作りのノウハウ、数々の思いがこもった作品も紹介されており、心がほっこりした。注意書き等も筆者の色々な気遣いがあり良書。2022/09/04