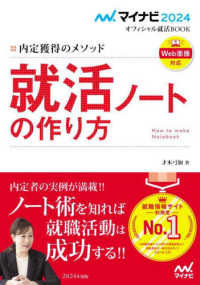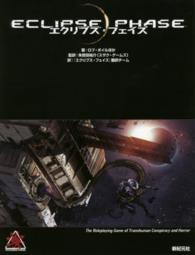内容説明
ウィーンの約200年に及ぶ弦楽四重奏団の歩みを綴った歴史書。活動と歴史的推移を論述し、ウィーンの名弦楽四重奏団の誕生と栄枯盛衰の軌跡を総括する。その録音についても、耳で確かめられる生きた資料として重点的に取り上げた。さらに、現在活躍するウィーンの弦楽四重奏団の動向を捉え、明日への展望を予測する。
目次
第1章 1755年から1830年頃(ベートーヴェンに作曲意欲を起こさせた、世界初の職業弦楽四重奏団の誕生)シュパンツィヒ四重奏団と同時代の弦楽四重奏団
第2章 1830年から1850年頃(ベートーヴェン後の弦楽四重奏団の低迷期)演奏会が極端に低調になった…それを救ったのは…
第3章 1850年から1880年頃(ウィーン・フィルの首席奏者たちが弦楽四重奏団を結成する伝統を築いた、黎明期のウィーン・フィル楽員による弦楽四重奏団)ヘルメスベルガー四重奏団と、同時代の弦楽四重奏団
第4章 1880年から1930年頃(その1)(ブラームスやドヴォルザークの作品を意欲的に紹介した発展期のウィーン・フィルの楽員による弦楽四重奏団)ロゼー弦楽四重奏団と、同時代の弦楽四重奏団
第5章 1880年から1930年頃(その2)(シェーンベルク、ベルク等の作品紹介に尽力し、ウィーンに新風を吹き込んだ新ウィーン楽派の弦楽四重奏団)新ウィーン楽派に対応するコーリッシュ弦楽四重奏団、ガリミール弦楽四重奏団、及び同時代の弦楽四重奏団
第6章 1930年から1950年頃(第二次世界大戦前後の混乱期、ウィーンの伝統を守ったウィーン・フィル楽員による弦楽四重奏団)ウィーン・フィルハーモニア四重奏団、シュナイダーハン弦楽四重奏団、ヴァイスゲルバー四重奏団
第7章 1940年代から1970年頃(LPレコードによりファン層が飛躍的に広がった時代。第二次世界大戦前後のウィーン・フィルの楽員による弦楽四重奏団)LP初期の落とし子たち―バリリ四重奏団、ウィーン・フィルハーモニー弦楽四重奏団、ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団
第8章 1950年代以後(ウィーン・フィルの弦楽四重奏団が取り上げないジャンルを独自に開拓した、ウィーン交響楽団の楽員による弦楽四重奏団)ウィーンはウィーンでも…
第9章 1960年代から1990年代(ウィーンの弦楽四重奏団200年史を総括する、伝統奏法で歴代最高位の理想郷を実現したヴェラー弦楽四重奏団の誕生と悲劇)ヴェラー弦楽四重奏団の悲劇
第10章 21世紀初頭、現在のウィーンの弦楽四重奏団―現状と将来への展望
著者等紹介
幸松肇[コウマツハジメ]
早稲田大学第一商学部出身。ヴァイオリンと作曲を故池譲氏に、弦楽四重奏の演奏法を故浅妻文樹氏に、指揮法を紙谷一衛氏に師事。在学中は、早稲田大学交響楽団でヴァイオリン奏者として活躍。東芝EMI株式会社では、プロデューサーとして、弦楽四重奏のLP、CDを制作(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。