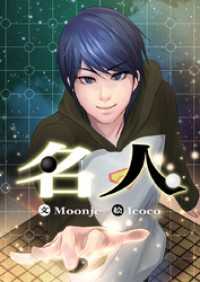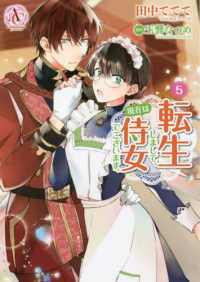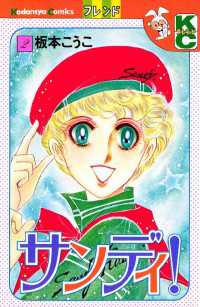出版社内容情報
《内容》 人間の精神や行動、社会関係は、きわめて複雑な現象である。あまりにも複雑で、しかも個別的なので、法則性など存在しえないと思われるかもしれない。あるいはまた、自分を含む人間一般の精神や行動、社会関係には法則性などないほうが、夢とロマンがあってよいと感じられることがあるかもしれない。 しかし、この複雑な人間にかかわる現象についても、現象に内存する法則性を明らかにすることは不可能ではないし、さらに法則性に基づいて予測や計画、介入をはかることも不可能ではない。社会科学・行動科学の目的は、人間にかかわる現象に内存する法則性を明らかにすることであるし、保健・医療・看護・福祉・教育なんどの実践領域では、法則的な知識に裏づけられた予測や計画、介入方法の確立が求められている。それゆえ、社会科学・行動科学の研究者や実践家、そして研究者や実践家になろうとする学生には、法則性を解明するための手段・研究方法についての知識が不可欠である。 本書は、法則性を解明するための手段としての調査と実験、データ処理の方法についてわかりやすく解説した入門書である。はじめて調査や実験をしようとするときには、まず本書を通読し、そのうえでもう一度読み直しながら作業を進めれば、失敗のリスクを最小限におさえることができるだろう。また本書を一度通読しておけば、調査や実験の報告を読むときにも、研究方法の適否を容易に判断できるであろう。 --著者まえがきより-- 調査と実験、データ処理の方法を学ぶ人がはじめて読む本として企画され、出版された本書は、学生の副読本としても広く用いられています。著者のまえがきにもあるとおり、本書を通読すると、調査というものがどのような手順を踏んで行われるものなのか、全くの素人にもその全体像がのみこめるはずです。そして実際に作業を行う際には、まさに手引書として役立つでしょう。 また、社会学者と心理学者の共著であるという意義も大きく、調査や実験の場での、専門領域を越えた協力関係のためにお互いの研究方法を知ることにも役立ちます。 具体的な内容は、以下のとおりです。 第1章は、実証研究の進め方として、研究のプロセス、研究対象のモデルが提示され、データの収集と分析方法の決定という本書の緒言にあたる紹介がなされています。ここで、研究自体の枠組みについて失敗例があげられ、失敗をおかさないためのチェックリストも作られています。 第2章には、現象をとらえるための変数とその測定についてです。独立変数と従属変数の概念や、変数測定にあたっての妥当性、ならびに信頼性、そして尺度の開発について詳述されています。 第3章は、調査の計画と進め方が具体的に記述されています。サンプリングの問題やデータ収集の方法、調査票の作成、調査の実施と具体例をあげながら説明されています。 第4章は、実験の計画と進め方です。実験は実証的研究のなかで調査と並んで重要な研究方法ですが、これについても、実験計画の基本的な考え方が、例にそって、具体的に問題点を論述するかたちで述べられています。実験計画のなかで重要なテーマとなる統制についても記述されています。 第5章は、データの集計と分析について、第6章は、分析結果の一般化について、第7章は、統計分析の展開についてで、 この3つの章の詳細な記述は、統計を苦手と考える人でも統計が理解できるほどの充実した内容です。 第8章には、研究結果の発表、論文の書き方がまとめられており、学会誌、学術誌へ投稿する際の留意点などにも触れられています。 巻末には、本書にふれて、さらにこの領域について勉強したくなった人のために、わかりやすい参考書が紹介されており、有益でしょう。また、付表として、t分布表、F分布表、およびχ2分布表がついています。 ほかに、30項目のコラム欄があり、やや高度な事項や社会学と心理学の間で見解に相違のある事項についての説明が加えられています。ここでは、ダミー変数、オーバー・サンプリングといった基本的な事項に加えて、たとえば回答拒否に対する対処方法や調査に協力して回答してくれた対象者に対する謝礼についてなど、知りたいことが満載されています。 社会科学、行動科学、心理学、保健、医療、看護、福祉、教育などの領域で研究者や専門家になろうとする学生、あるいは現在、研究を進めているリサーチ従事者の方々には、是非とも座右の書として、一読、再読していただきたい1冊です。 《目次》 実証研究の手引き--目次 ・本書の使い方 ・第1章 実証研究の進め方 I.研究のプロセス II.モデルの改良 III.データの収集・分析方法の決定 IV.いくつかの失敗例 V.失敗しないためのチェックリスト ・第2章 現象をとらえる-変数とその測定 I.変数とはなにか II.モデルのなかの変数 III.変数の測定 IV.測定値の水準 V.測定の妥当性 VI.測定の信頼性 VII.尺度の一次元性 VIII.尺度の開発と使用 ・第3章 調査の計画と進め方 I.調査対象の選定 悉皆調査と標本調査 サンプリング 母集団統計の検討 非標本誤差と標本調査の現実 標本数の決定 II.データ収集の方法 III.調査票の作成 設問の形式 質問文の作成 選択肢の設け方 調査票の構成 IV.調査の実施 依頼 調査員の訓練と監査 データ入力とデータ・クリーニング ・第4章 実験の計画と進め方 I.実験計画の考え方の基本 II.1変数の分析 度数分布表 代表値 散布度を表す統計測度 分布の歪みと尖りを表す統計測度 順位に基づく統計測度 III.2変数・質的データの分析 クロス表 クロス表の関連度の係数 IV.2変数・量的データの分析 相関係数と共分散 回帰係数と回帰定数 相関係数の意味 ・第6章 分析結果の一般化-推定と検定の考え方と実際 I.標本の統計計量と母集団の統計量 推測統計が必要になるとき 標本統計量の分布 II.推定の考え方 III.検定の考え方 検定はなぜ必要か 研究のための仮説と統計的仮説 帰無仮説を棄却する手順 危険率と棄却域 第一種の誤りと第二種の誤り IV.検定の実際 実際に検定を行う際の手順 平均値の差の検定 分散の差の検定;F検定 比率の差の検定 相関係数の有意性検定(無相関の検定) 相関係数の差の検定 クロス表の関連度の検定(独立性の検定) ・第7章 統計分析の展開-多変量解析 I.なぜ ”多変量”解析か II.さまざまな多変量解析 III.多変量解析の実際 重回帰分析 分散分析 因子分析 ・第8章 研究結果の発表-論文の書き方 I.科学論文の構成 II.原稿の準備・投稿から掲載まで III.難関を突破するコツ ・わかりやすい参考書 ・付表 1.正規分布表 2.t分布表 3.F分布表 4.x2分布表 ・索引