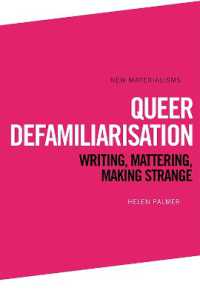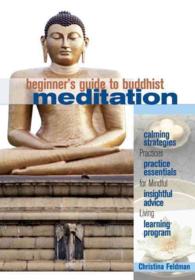出版社内容情報
本書は「やどかりブックレット1 精神障害者にとって働くとは」の第2弾です.労働省の職員の方々に対する私たちメンバー3名,職員1名の講演を行った記録です.精神障害者にとって働くということは憧れです.しかし,現状は厳しい.初期において,一般就労は社会復帰したこととみなされている時がありました.しかし,病気が回復し,就労すると再発をくり返す中で,どうも一般就労という形をとらなくてもよいのではないか,という考えに変わってきました.また,社会復帰という言葉もあまり使われなくなってきたようです.それぞれが社会の中で生きていける,それは生活保護という形をとっても,地域でごく当たり前に生きることが大切で,そんなに就労に拘ることはないし,人間が尊厳をもって生きる……それでいいのではないかという考え方が出てきました.
世の中にはいろいろな人間がいて,いろいろな生き方がある.そんなことを私たちは本書で伝えていきたいと思います.そして,働くということの原点はお金だけではない.やはり,人間が働く喜びを持って生きていく,そんなことを感じていただけたら幸いです.(やどかりブックレット編集委員 星野文男 はじめにより抜粋)
発刊にあたって
はじめに
1.4人の体験発表・働く
ともに働く中から精神障害のことをわかってほしい 香野英勇
向精神薬を飲んで働くことの辛さ
社会の中での居場所を求めて
薬を隠れて飲もうとすることで被害的になる
向精神薬は副作用が強い
病気を隠すことの辛さ
自分が認められることの喜びがある福祉工場
病気をする前の自分を取り戻している
協働の中でこそ精神障害者のことがわかる
素朴な質問が出せる職場 星野文夫
精神障害の2大症状
幻聴を抱えながら多忙な会社に就職
サラリーマンのつき合いから浮いた存在に
役所の臭いがして行けなかった職安
職場の環境にどうしても馴染めず
父親の病気入院を期に気を入れて働き始める
精神障害者というレッテルを貼られるのが嫌で
やどかり情報館には仕事の経験がない人がかなりいる
差別でなく区別することが大切
素朴な質問が出せるような職場が必要
自分が認められたいから 大村祐二
24歳で発病,対人恐怖症を患う
34歳で幻聴
精神障害当事者が企画から携わるブックレットシリーズの第6段.精神障害者にとって働くとはどういう意味を持つか1つの例として,福祉工場で働く3人のメンバーと1人のスタッフの話をまとめました.
内容説明
本書は「やどかり里ブックレット1精神障害者にとって働くとは」の第2弾です。労働省の職員の方々に対する私たちメンバー3名、職員1名の講演を行った記録です。
目次
1 4人の体験発表・働く(ともに働く中から精神障害のことをわかってほしい;素朴な質問が出せる職場;自分が認められたいから;雇用に新しい機会を導入した福祉工場)
2 質疑応答(生活者としての自信が障害をプラスに変える;障害者が地域に根づくことを願って体験発表会を;質のよい仕事を誠実にこなすことで;今後障害の開示の方向を進めてください ほか)
著者等紹介
星野文男[ホシノフミオ]
やどかりブックレット編集委員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。