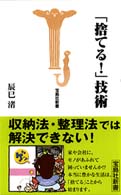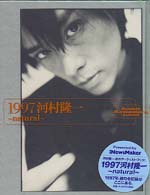内容説明
落語つき世相放談。
目次
相像力レッスン(「だくだく」一九九八年五月二十三日)
ナンセンスを笑え(「粗忽長屋」一九九六年十月二十六日)
マスコミのようなもの(「バールのようなもの」一九九七年十一月六日)
野暮はヤだね(「文七元結」一九九八年十月十六日)
僕らは副音声(「井戸の茶碗」二〇〇〇年六月二十七日)
著者等紹介
立川志の輔[タテカワシノスケ]
1954年富山県生まれ。76年に明治大学経営学部を卒業したのち、演劇活動や広告代理店勤務を経て、83年に立川談志門下入門。にっかん飛切落語会奨励賞、文化庁芸術祭賞など受賞多数。90年に立川流真打ち昇進。「志の輔らくごin下北沢」ほかの定例ライブを積極的に行う一方、NHK「ためしてガッテン」の司会でも活躍
天野祐吉[アマノユウキチ]
1933年東京生まれ。創元社、博報堂などを経て独立、1979年に「広告批評」を創刊する。同誌編集長、発行人を経て、現在は主にマスコミを対象とした評論やコラムの執筆、テレビのコメンテーターとして発言
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
よし
4
テレビ「タメシテガッテン」の軽妙でユーモアにあふれた司会でお馴染みの志の輔。彼の落語を初めて「紙上ライブ」で聞く(読む)。江戸と現代を橋渡しする「つなぎ」が絶妙だった。「テレビでは、主音声・・建て前的、寄席では、副音声・・本音も際どいこともいう」この使い分けがあると分かった。天野氏との対談は、「話の後始末」としての面白さがあった。「寄席の空気が芸の質を決定する。・・そういう場、こういう濃厚なコミュニケーションの場、昔はこれが当たり前だった。」彼の落語を生で聴きたくなった。2018/04/14
がしょー
0
対談と落語が交互に書かれている。この本が出版されたのは2000年だけど対談のお話は現代社会でも通用する。というか今も社会は変わらないままなんだなと嘆く。テレビはみんなが知っていることしか喋れない。70歳まで働き続ける日本人(下手すりゃ70歳越える)。人間の本能を包み隠していくこの現代社会に異議を唱えたくなる一冊だった。ようするにいい本だった。2016/10/23
mayumi
0
落語はもちろんのこと、対談も面白かった。落語の奥深さがかいま見えたような気がする。独演会で購入。2013/06/14
みにころ
0
面白かった~(^^)ナマ落語も聞きたいな。2012/12/12
ちょーのすけ
0
8年ぶりくらいの再読。いい落語、楽しい薀蓄。2010/05/31