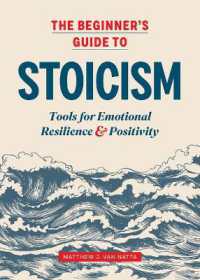内容説明
本書に一貫した筆者の態度は、戦後の流れを全く度外視したものです。すなわち「誰にでも出来る○○」「すぐに出来る△△」という類のものではなく、さらに試験やコンクールなどの競争の為のテクニック習得ということを全く目的としていません。あくまでも音楽表現の道具としてのピアノについて、その構造に照らして奏法の問題を考えること、また音楽という営み全体の中で演奏という行為の意味を考えることを旨としました。
目次
タッチと音色
音量と音楽表現
ダンパーとペダル
リズムとアーティキュレーション
奏法についての考察
椅子の坐り方と姿勢
音楽的テクニックの習得
音楽的能力とは何か
音楽と感情
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
兎乃
17
直面する問題がすなわち課題であり、さて、この身体をどうするか?この心をどう使うか?楽器に触れるとき、それは愛を学ぶ瞬間なのかもしれない。エロスからフィリア、フィリアからアガペ。相手(ピアノ)の身体をよく理解すること。その身体を幸せにするために、私の身体ができること。ずっとずっと学ぶために。 2013/02/16
fishdeleuze
11
ピアノのテクニックとは、ピアノの構造的特性を元にピアノがもつそのパフォーマンスを最大限に出すための一種の身体技法であること。良い演奏とは音楽的イメージを具現化することであり、豊かな音楽的イメージを得るためには、音楽の解釈のみならず、即興演奏的な能力、すなわち音楽的な自発性(spontaneous)が重要であること。身体技法としての演奏という概念は、最初読んだ時驚いたものだが、最小限の力(動き)で、最大限のパフォーマンスを得るという点では、合気道などの武術に似ている。繰り返し読みたい良書。2013/01/21
ヨハネス
2
ピアノの構造、身体の構造など科学的に説明されているので納得できます。地域、時代により間違った弾き方、教え方が流行したのを知り、不幸なことだと思いました。ピアノを学習する人すべてが読まれるとよいと思います。歴史的なピアニストが遺した名演奏のリストがあり、聴いてみたいと思うのですが、ラジオでたまに耳にすると音質の悪さばかり気になり、本来の演奏の魅力が聴きとれず残念です。2015/04/17
Nami Yamamoto
1
ついぴを通じて知りあった木下さん主催の講演会で初めて知った作曲家の雁部一浩さんの名著。理系出身だけあって合理的にピアノの構造から解き明かし、例えばペダルを踏んだ後も指で鍵盤を押さえ続けることがいかにナンセンスかなどを説明してくれる。打鍵の際の雑音も考慮するもんだとか、ピアノとフォルテの差は打鍵の速さだけだとか、考えたこともなかった。芸術表現にも理論って大切なんだと今さら痛感。楽理も勉強したくなってきた。最後の方は理屈っぽすぎて共感できない部分もあったけど、読んで良かった。もう一度、読み直してみようっと。2016/07/27
ハッチ
1
ヤマハの音楽の考え方と似ていた。2016/06/07
-
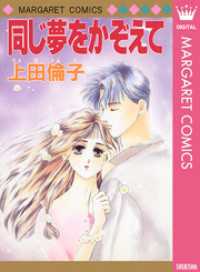
- 電子書籍
- 同じ夢をかぞえて 傑作読み切り集 2 …
-

- 和書
- 鉄の棺