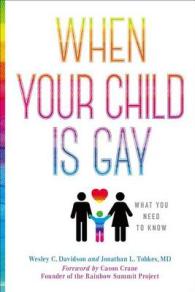内容説明
各務三郎が「ミステリマガジン」編集長時代を、皆川博子が少女時代の読書体験を、三谷幸喜が「作戦もの」の魅力を、法月綸太郎がアントニー・バークリーを、石上三登志がミステリの楽しみ方を、松岡和子が戯曲を翻訳する喜びを、和田誠が戦後のアメリカ文化を、はじめて語ってくれた。
目次
ミステリがオシャレだったころ(各務三郎)
皆川博子になるための136冊(皆川博子)
理想の作戦ものを求めて(三谷幸喜)
本格推理作家はアントニー・バークリーに何を読みとるのか?(法月綸太郎)
札つきファンのミステリの接し方(石上三登志)
戯曲を翻訳する幸せ(松岡和子)
バタくささのルーツを探る(和田誠)
著者等紹介
小森収[コモリオサム]
1958年福岡県門司市生まれ。フリーランス編集者。1984年より十二年間、週刊劇評紙『初日通信』を編集・発行し、『TOKYO芝居探検隊』や宝島モダンクラシックプレイズ全六巻を担当した。その後、文芸書専門となり、山本文緒『パイナップルの彼方』『ブルーもしくはブルー』、篠田節子『夏の災厄』、三谷幸喜『古畑任三郎』、黒崎緑『未熟の獣』などを手がける
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
本木英朗
13
日本の現代評論家のひとりである、小森収のインタビュー集のひとつである。俺は今までに、2004年・2018年に1回ずつ読んでいて、今回で3回目だ。各務三郎から始まって、和田誠で終わるインタビュー集であるが、どれもこれも本当に凄かった!の一言である。中でも俺的には、三谷幸喜と法月綸太郎の二人には、本当に大満足であったのだよ、ウンウン。またいつか、4回目に挑戦かな、ウフフ!!2025/03/19
本木英朗
12
再々読。やはり法月綸太郎のバークイー論には頭が下がる。どうやって書いたのか、そしてどうやって書かなかったのかなどがよく分かる。ちなみに『第二の銃声』『殺意』『ジャンピング・ジェニイ』はすべて深く立ち入っているため、そこはご注意を。他の作家(各務三郎や和田誠など)も面白かった。これは小森収のインタビュー力がすごいと言える。また10年後辺りに読みたいものだ。2019/01/06
pulp
5
初刊行から20年以上経って、この12月に東京創元社の文庫に入る。文庫版には北村薫が追加されるとのこと。しかしインタビュアー小森さんで、法月綸太郎、石上三登志、和田誠に、北村って来ると、どうしても瀬戸川猛資さんを思い出してしまう(この本が出る数年前に逝去。いまだに私は瀬戸川さん的なものを追い求めている)。今回再読して面白かったのは石上さんのミステリ論かな。このひと、自分の中で評価が上がったり、下がったり、上がったり…… その石上さんも、それから和田さんも、もういないのか。あっちで楽しく喋っているのかな?2023/10/26
坊っちゃん
2
★★★1/2 2002年刊。インタビュー集。各務三郎、皆川博子、三谷幸喜、法月綸太郎、石上三登志、松岡和子、和田誠。それぞれに人に歴史ありで読み応えあり。しかし中にはアントニー・バークリーについてネチネチと語るだけの不要な人も。その人に続いて登場の石上三登志が、新しいもの(ミステリ)がピンとこないのか、と小森収に聞かれて、「新本格からです。(中略)最初の二、三ページでネタがわかってしまう。」とバッサリ斬ったのは拍手。続いて島田荘司やデクスターへの批判も。(コメント:2019/04/09)2019/04/09
青縁眼鏡
2
再読。初読のときは法月倫太郎さんのお話を楽しく読んだ気がするが、今回は松岡和子さんの話が興味深かった。ここ数年お芝居を観る機会が増えたからだろう。そして、皆川博子さん。今からでも皆川博子さんのようになれるかしら。2009/12/29