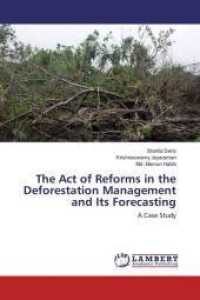目次
第1章 チーム援助の考え方(チーム援助の発想とシステム;援助チームの作り方・進め方;援助チームシート、援助資源チェックシートの使い方;チーム援助の実践に向けて)
第2章 小学校における実践(校内支援委員会によるチーム援助;ADHDとLDを併せもつ子どもとのかかわり;力尽きて不登校になった子どもへの援助;学校と適応指導教室が協力した実践;場面緘目で教室に居られない子どもとのかかわり)
第3章 中学校における実践(2学期から元気をなくした生徒へのかかわり;配慮を要する生徒へのかかわり;「保健室登校」生徒へのチーム援助;アスペルガー症候群の生徒とのかかわり;三つの機関の協働を円滑にすすめた援助シート)
第4章 高校における実践(留年した生徒へのかかわり;自傷行為が心配な生徒へのかかわり;教育相談委員会を生かしたかかわり;保健室登校から教室復帰、進路決定までのかかわり)
著者等紹介
石隈利紀[イシクマトシノリ]
現在、筑波大学大学院人間総合科学研究科教授。筑波大学心理・心身障害教育相談室相談員。学校心理士・臨床心理士。アラバマ大学大学院博士課程行動科学研究科修了。Ph.D(学校心理学)。カリフォルニア州の小学校のスクールサイコロジスト(インターン)、筑波大学学生相談室カウンセラーなどを経て、現職
山口豊一[ヤマグチトヨカズ]
現在、跡見学園女子大学文学部臨床心理学科教授、同大学大学院教授、同大学附属心理教育相談所長。学校心理士・臨床心理士。茨城大学大学院教育学研究科修了(教育学)。茨城県の公立小・中学校の教諭として17年間勤務する。その後8年間、茨城県教育研修センター教育相談課の指導主事として教育相談に関する教員の研修、教育相談に関する研究、教育相談事業に携わる。その間、「学校心理学」と出会い、これからの学校教育を支えるセオリーはこれだと確信する。平成15年より茨城県スクールカウンセラーとして中学校で生徒と格闘中。「理論と実践(チーム援助)」のつなぎをめざす
田村節子[タムラセツコ]
現在、スクールカウンセラー、茨城キリスト教大学文学部兼任講師、たむら小児科クリニックカウンセラー等、兼務。学校心理士・臨床心理士。筑波大学大学院教育研究科修了(教育学)。日立市教育研究所・水戸市総合教育研究所教育相談員、茨城県カウンセリングアドバイザーなどを経て、現職
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。