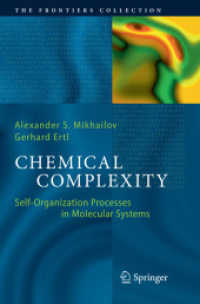目次
1 方法・対象―社会学の新しい見方(言葉に抵抗する技術;お邪魔な科学;問題の社会学者;知識人は賭けを免れているか;どうやって「自由な知識人」を解放するか;社会学者の社会学のために;社会学者のパラドックス)
2 言語(話すとはどういうことか;場のいくつかの特性;言語市場;検閲;「若者」とは言葉でしかない)
3 趣味と芸術(音楽愛好家という種の起源と進化;趣味の変容;人はどのようにしてスポーツ好きになるのか;オート・クチュールとオート・キュルチュール;それにしても、誰が「創造者」を創造したのか)
4 文化と政治(世論なんてない;文化と政治;ストライキと政治行動;知能のラシスム)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
またの名
11
わずかな資本しか持ち合わせてないゲームの新参者は転覆・異端の戦略で資本を独占する正統派の権威者に対抗するが(物事について奇を衒った感想を提示したり)、ゲームが立脚する究極的な台座を揺るがしはせずむしろ蘇生させようとする、と指摘。「学者が独占する難解な文化資本を告発すると言っておきながら、言葉遣いが難解で告発するはずの独占をもう一度復活させてるんじゃないですか」と質問者に詰め寄られるブルデューの立場は、文化資本の貧しい出身ながら高度な学術の世界で仕事を提示するジレンマを抱えつつ、まさにそれを対象化。入門用。2018/05/16
roughfractus02
8
入門書の位置付けとなる本書は、動態として捉えられる文化資本を、文学、音楽、芸術、スポーツ、モードの具体例で概説し、社会学自身の問題に対する自らの問いやジレンマも示しつつ進む。単位となる行為者は差異の集合だが、それらが心的性向(ハビトゥス)を作り行動(プラティック)するゆえに視点を持ち、差異は差別化に変わる。一方著者は行為者同士が生み出す界(接触しぶつかり合う交互的作用)に注目する。界が文化資本に浸透する行為者の視点の拘束を生産する権力構造を前景化すると、「若者」は言葉でしかなく「世論」もない世界が見える。2024/05/12
takao
2
ふむ2024/09/27
いまにえる
0
特に序盤の方法・対象の章は社会学の社会学的考察もあったが、全般としては解説で言っている通りブルデュー社会学の入門といった感じであった。彼はハビトゥスなどの基本概念で教育や階級について主に論じている。身の回りのあらゆることを疑う社会学の基本的スタンスを学べたと思う。2017/10/07
-
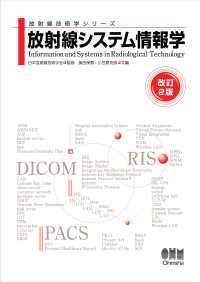
- 電子書籍
- 放射線技術学シリーズ 放射線システム…