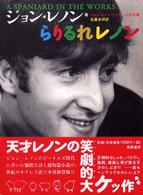内容説明
いつの時代も日本人は、寄鯨を、海からもたらされる贈り物としてありがたく受け取ってきた。たしかに日本には捕鯨の伝統や文化がある。しかしそれは今、ややもすれば感傷的な自然保護や感情的なナショナリズムで語られてしまう。はたして日本人は鯨とどのように関わってきたのか。かつて西海捕鯨の島として栄えた長崎県生月島に暮らす著者が、日本捕鯨の歴史をたどる。
目次
第1章 日本捕鯨の概観
第2章 初期捕鯨時代
第3章 古式捕鯨業時代前期
第4章 古式捕鯨業時代中期
第5章 古式捕鯨業時代後期
第6章 古式捕鯨業時代の鯨の利用
第7章 捕鯨にまつわる文化
第8章 近代捕鯨業時代前期
第9章 近代捕鯨業時代後期
著者等紹介
中園成生[ナカゾノシゲオ]
1963年福岡市生まれ。熊本大学民俗学研究室卒業。現在、長崎県北松浦郡生月町の博物館島の館学芸員。生月の文化である捕鯨やカクレキリシタンをはじめとする民俗研究に従事。著書に「生島のかくれキリシタン」、共著に「かくれキリシタンの聖画」「民具」など
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ishida Satoshi
1
読了。面白い。本書では、今日の捕鯨論争が「可哀想だ」という感情論や単純な日本バッシングに陥らずに、そもそも日本人、あるいは欧米人がクジラとどのように関わってきたかを歴史資料を紐解きながら、明らかにしていきます。日本で捕鯨の伝統は西日本中心なわけですが、かつては島に偶然流れ着いたクジラを漁師集団が保存食や鯨油生産に当てるために、そこそこに捕獲し、地域内で消費されていたもの。いわば受動的捕鯨でした。しかし、「鯨組」といった組織捕鯨の産業化に始まり、いつの頃からか、網捕鯨から砲殺捕鯨へと捕鯨方法も近代化し、沿岸
-

- 電子書籍
- 科学的思考入門 講談社現代新書
-

- 電子書籍
- 海皇紀(22)