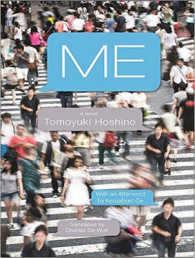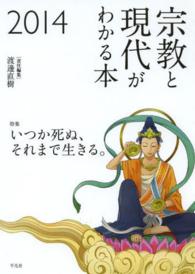出版社内容情報
~発刊にあたって~
トライボロジーという言葉が誕生したのは30年以上も
前の1966年のことであり,近年すっかり定着した感が
ある。それに伴いこの技術も科学技術の表舞台に出て
おり,自動車や鉄道などで,トライボロジーの問題が最
後の大きな壁になっている分野も少なくない。
本書は10年ほど前,当社で同時期に出版した「トライ
ボロジーデータブック」及び「摩耗機構の解析と対策」と
いうトライボロジー分野の書籍を,編集者及び著者の了
解を得て1冊にまとめたものである。まとめたと言っても,
内容を吟味して編集し直したのではなく,1編,2編という
形で全く機械的に合本にしたものであり,お互いに相手
の編に対して責任は持っていない。従って内容的に一部
重複している部分があるが,まだまだ解明されていない
部分の多いこの分野の現状からすると,あまり大きな問
題ではない。同一の現象が様々な分野,様々な角度か
ら説明されている現状からしても,むしろ重複部分に関し
ては深い理解が得られるものと考えてよい。
そうはいっても,別の編集者,著者によって作成された書籍であるから,当然,
発刊において目指すものは異なっている。第1編「トライボロジーデータブック」は
内容を限定せず,トライボロジー全般についてのいわゆるデータブックの形を取っ
ている。表や図が多く収録されており,設計者やユーザが手元に置いてすぐに使え
るまさにユーザオリエンテッドなものになっている。
それに対して第2編「摩耗機構の解析と対策」は,その名の通り,トライボロジー
の中でも“摩耗”の問題に焦点を絞り,摩耗の機構に関する部分にかなりのページ
を割いている。一般的な摩耗理論の紹介のあと,材料別及び要素別にそれぞれの
特徴的な摩耗現象を説明している。
また,読者の便宜を考え目次は通してページを振り,索引項目は第1編と第2編を
合わせて記載した。
以上に述べたように目指すものが異なる2冊の書籍を合本したことによって本書
は,トライボロジーに関わる広範囲の技術者に対して有益な情報を与えてくれる
書籍に変身している。機械的因子,界面化学的因子,材料学的因子など,様々な
因子が複雑に関与するトライボロジー現象に対して,100%満足する解答を与えてく
れる書籍はないといってよい。そのような現状の中で,本書には問題解決の手がか
りになる多くのヒントが示されている。
第1編 トライボロジーデータブック
第2編 摩耗機構の解析と対策
監修
監修
木村 好次
東京大学名誉教授・香川大学名誉教授
工学博士
野呂瀬 進
帝京大学 理工学部 機械精密システム工学科
教授 工学博士
編集
執筆者
星野 道男
石油連盟ISO石油製品国内委員長
野呂瀬 進
帝京大学 理工学部 機械精密システム工学科
渡辺 真
(財)日本産業技術振興協会
教授 工学博士
尾池 守
石巻専修大学 理工学部 機械工学科
執筆者
教授 工学博士
星野 道男
石油連盟 ISO石油製品国内委員長
田中 章浩
(独)産業技術総合研究所 新炭素系材料開発研究
渕上 武
日本潤滑剤?? 技術顧問
センター 表面機能制御材料チーム チーム長
川邑 正男
?叶?邑研究所 代表取締役
水谷 嘉之
岐阜大学 産官学融合センター
産学連携コーディネーター
内山 吉隆
金沢大学 工学部 機能機械工学科
教授 工学博士
志摩 政幸
東京商船大学 商船学部 交通機械工学講座
教授 工学博士
堀内 克英
スターライト工業??
関口 勇
工学院大学 工学部 機械工学科 教授 工学博士
Project Next チームリーダー
畑 一志
出光興産?? 営業研究所 主任研究員
三橋 健八
横浜ゴム?? 標準化担当 主幹 工学博士
澤本 毅
(日本精工?? 基盤技術研究所 主席研究員)
山口 洋一
横浜ゴム?? タイヤ材料設計部
福岡 辰彦
大豊工業??
井上 浩一
?鞄月ナ ディスプレイ・部品材料社
材料部品開発部長
滝 晨彦
岡山理科大学 工学部 機械システム工学科
教授 工学博士
水谷 嘉之
岐阜大学 産官学融合センター
産学連携コーディネーター
河原 由夫
?劾OKグループサービス
神崎 福
(日清紡?? 西新井化成工場
副工場長兼摩擦材部長)
寺岡 利雄
東洋酸素?? ATD 技師長
木川 武彦
日本精工?? 鉄道・航空技術部 嘱託
辻村 太郎
(財)鉄道総合技術研究所 摩擦材料研究室 室長
倉知 祥晃
倉知技術事務所 代表
(日産自動車株式会社 材料研究所)
三宅正二郎
日本工業大学 工学部 教授 工学博士
岩松 久保
石川島播磨重工業?? 技術本部 品質保証部
専門部長
浦 晟
長崎大学 工学部 副学長 教授 工学博士
( )内の肩書きは執筆時のものです
倉橋 基文
大同特殊製鋼?? 取締
第1編 トライボロジーデータブック
序 ユーザーオリエンテッドトライボロジー
第1章 潤滑油・グリース
第1節 潤滑油
第2節 グリース
第2章 固体潤滑
第1節 固体潤滑剤の種類と特徴
第2節 固体潤滑被膜
第3章 高分子摺動材のトライボロジー
第1節 プラスチック材料の摩擦・摩耗と軸受設計
第2節 ゴムの摩擦・摩耗試験機と試験データ
第4章 セラミックスのトライボロジー
第5章 表面分析のトライボロジーへの応用
第2編 摩耗機構の解析と対策
第1章 摩耗現象と研究動向
第2章 摩耗機構の解析
第1節 凝着摩耗とその機構
第2節 アブレシブ摩耗とその機構
第3節 疲れ摩耗とその機構
第4節 腐食摩耗とその機構
第5節 フレッチング摩耗とその機構
第3章 各種材料の摩耗とその対策
第1節 金属および金属複合材料の摩耗と対策
第2節 プラスチックおよびプラスチック複合材料の摩耗と対策
第3節 セラミックスおよびセラミックス複合材料の摩耗と対策
第4章 各種機械要素の摩耗とその対策
第1節 転がり軸受の摩耗と対策
第2節 すべり軸受の摩耗と対策
第3節 歯車の摩耗と対策
第4節 シールの摩耗と対策
第5節 ブレーキの摩耗と対策
第5章 各種機器の摩耗とその対策
第1節 鉄道用機器の摩耗と対策
第2節 自動車機器の摩耗と対策
第3節 情報機器の摩耗と対策
第4節 産業用機器の摩耗と対策
第6章 耐摩耗表面処理技術
第7章 摩耗試験法
第8章 摩耗診断法
第1編 トライボロジーデータブック
第1章 潤滑油・グリース
第1節 潤滑油
1.潤滑剤の働きと種類
1.1 潤滑剤の働きとそのため必要な性質
1.2 潤滑剤の種類
1 形態による分類 2 基油組成による分類
2.潤滑性に関連する添加剤
2.1 潤滑性に関連する添加剤
2.2 その他の添加剤
2.3 添加剤の相互作用と配合の決定
3.設計と選定に必要な潤滑油の特性
3.1 粘 性
3.2 密 度
3.3 その他の物理的性質
4.潤滑油各論
4.1 潤滑油の販売形態
4.2 自動車用潤滑油
4.3 舶用潤滑油
4.4 工業用潤滑油
4・5 金属加工油剤
5.潤滑油の試験法・評価法
5.1 試験の種類
5.2 試験の目的と適用上の注意
5.3 潤滑油の試験による潤滑管理と故障予知
6.潤滑油の選定基準とトラブル対策
6.1 機械要素による潤滑油の選定
1 すべり軸受 2 転がり軸受
3 歯車 4 すべり案内面と湿式摩擦機構
6.2 潤滑油からのトラブル対策
第2節 グリース
1.グリース潤滑
1.1 グリース潤滑の特性
1.2 グリース潤滑の利点と欠点
1.3 油潤滑との比較
2.グリースの性質と実用性態
2.1 グリースの流動特性
2・2 グリース潤滑に特に必要な実用上の配慮
1 剪断安定性 2 基油と増稠剤の分離
3 低温使用限界 4 耐熱性と劣化
3.グリースの種類
3.1 組成による分類
1 増稠剤 2 基油 3 添加剤
3.2 用途による分類
1 一般用グリース 2 転がり軸受用グリース
3 自動車用シャシーグリース
4 自動車用ホイールベアリンググリース
5 集中給油グリース 6 高荷重用(固体潤滑剤入)グリース
7 ギヤコンパウンド 8 特殊グリース
4.グリースの試験法と評価法
4.1 流動特性
4.2 その他の性状
4.3 潤滑寿命試験
5.グリースの選定基準とトラブル対策
5.1 機械要素による選定
5.2 グリースからのトラブル対策
第2章 固体潤滑
第1節 固体潤滑剤の種類と特徴
1.固体潤滑剤の定義と種類
2.二硫化モリブデン
2.1 二硫化モリブデン原料の産地
2.2 選鉱法
2.3 二硫化モリブデンの潤滑理論
2.4 二硫化モリブデンの潤滑性
2.5 粉末粒径と潤滑性 2.6 純度に対する考え方
2.7 酸化について 2.8 適正添加量
2.9 油中分散安定性
3.グラファイト
3.1 グラファイトの原料 3.2 グラファイトの製法
3.3 グラファイトの潤滑理論 3.4 グラファイトの潤滑性
3.5 結晶性の影響 3.6 不純物の影響
3.7 粒度の影響 3.8 粒形の影響
3.9 パウダー選定
4.二硫化タングステン
4.1 製法の違い 4.2 酸化温度
4.3 二硫化タングステンの諸性質
4.4 その他
5.窒化ホウ素
5.1 BNの製造法 5.2 BNの諸元
6.フッ化黒鉛
6.1 フッ化黒鉛の製造 6.2 フッ化黒鉛の潤滑性
6?3 フッ化黒鉛の応用形態
7.メラミンシアヌレート
7.1 MCAの潤滑性 7.2 MCAの諸元 7.3 MCAの応用形態
8.PTFE
8.1 PTFEの製法 8.2 PTFEの諸性質 8.3 PTFEの使用形態
9.その他固体潤滑剤
9.1 合成硫化ニオブ 9.2 フッ化セリウム(CeF3) 9.3 その他
10.固体潤滑剤の使用形態
第2節 固体潤滑被膜
1.はじめに
2.固体潤滑被膜の被膜形成法による分類
2.1 擦り込み法 2.2 インピンジメント(Impingiment)法
2.3 インサイチュ(in-situ)法 2.4 金属マトリックス法
2.5 ドライプロセス法 2.6 結合(ボンディング)法
3.固体被膜潤滑剤の歴史
3.1 固体被膜潤滑剤の歴史 3.2 固体潤滑被膜の特徴
3.3 固体被膜潤滑剤の分類 3.4 有機結合固体潤滑被膜
3.5 無機結合固体潤滑被膜
3.6 固体被膜潤滑剤のコーティング方法
4.固体被膜潤滑剤の評価方法
4.1 固体潤滑被膜の評価に関係ある特性
5.固体潤滑被膜の応用
5.1 ホプキンスとキャンベルの固体潤滑被膜使用に際しての指針
5.2 固体潤滑被膜の応用例
6.おわり
第3章 高分子摺動材のトライボロジー
第1節 プラスチック材料の摩擦・摩耗と軸受設計
1.はじめに
1.1 摩擦現象
1.2 摩耗現象
1 凝着摩耗 2 疲労摩耗 3 アブレシブ摩耗
4 ころ生成摩耗 5 溶融摩耗 6 腐食摩耗,侵食摩耗
2.摩擦摩耗の試験法とその評価
2.1 摩擦の測定
2.2 各種摩擦摩耗試験機とその特徴
1 平滑な面を相手にした摩耗試験機
2 研磨粒子を相手にした摩耗試験機
2.3 摩擦と摩耗の表示法
1 摩擦の表示 2 摩耗の表示
2.4 試験規格
3.各種高分子材料の摩擦摩耗
3.1 摩擦.摩耗と接触圧力,摩擦速度.温度間の換算則
3.2 アブレシブ摩耗特性
3.3 凝着摩耗特性
4.各種高分子複合材の摩擦摩耗特性
4.1 PTFE系複合材料の摩擦摩耗
4.2 POM系複合材料
4.3 パラオキシベンゾイル(POB),ポリアミド(PAI)複合材料
4.4 PPS,PEEK,PES複合材料
4.5 ポリイミド(PI)系
4.6 液晶ポリマー材料
4.7 その他種々の複合材料
5.プラスチック軸受の設計
5.1 使用条件と材料選定
1 負荷条件 2 環境条件 3 相手軸条件
5.2 寸法設計
1 形状 2 軸受寸法精度
3 軸受の摩擦発熱と運転クリアランス
4 摩擦発熱 5 ハウジングとの嵌め合い
6 寸法設計例 7 プラスチック軸受メーカー
第2節 ゴムの摩擦・摩耗試験機と試験データ
1.はじめに
2.ゴムの摩擦・摩耗試験機,試験方法
3.摩擦試験の問題点
3.1 試験片および相手面の表面状態の安定化
3.2 すべり摩擦と転がり摩擦の関係
3.3 摩擦力に及ぼす要因の分類と実製品のシミュレーション
4.各種摩擦試験機と試験データ
4.1 傾斜法による試験
1 E. Rabinowiczによる方法(1951年)
2 山口による摩擦試験機(1989年)
4.2 引張法による試験
1 R. Schnumannによる摩擦試験機(1962年)
2 C. B. Pathepによる摩擦試験機(1956年)
4.3 回転円板法による試験
1 J. R. Whiteheadによる摩擦試験機(1950年)
2 E. Ruprechtによる摩擦試験機(1966年)
3 K. A. Grosch and H. H. Schulzによる氷上摩擦試験機
(1972年)
4 内山による摩擦試験機(1980年)
5 D. G. Flomによる摩擦試験機(1960年)
6 A. D. Robertsによる摩擦試験機(1986年)
7 澤による摩擦試験機(1986年)
8 J. J. Lazerationによる摩擦試験機(1987年)
9 E. Clamrbthによる摩擦試験(1968年)
4.4 振子法による試験
1 R. F. Westoverによる摩擦試験機(1962年)
2 C. S. Speerscheidenによる摩擦試験機(1962年)
3 D. Taborによる摩擦試験機(1955年)
4 B. E. Sabeyによる摩擦試験機(1964年)
4.5 ベルト法による試験
1 綱島による摩擦試験機(1963年)
2 W. F. Kernによる摩擦試験機(1967年)
3 D. F. Mooreによる摩擦試験機(1969年)
4.6 ドラム法による試験
1 F. W. Boggsによる摩擦試験機(1957年)
2 H. Riegerによる摩擦試験機(1969年)
3 A. D. Robertsによる摩擦試験機(1979年)
4.7 スライドによる試験
1 H. Riegerによる摩擦試験機(1969年)
2 K. A. Groschによる摩擦試験機(1963年)
3 D. Taborによる摩擦試験機(1966年)
4 G. M. Bartenevによる摩擦試験機(1965年)
5 G. M. Bartenev and A. Schallamachによる摩擦試験機
(1971年)
6 A. D. Robertsによる摩擦試験機(1971年)
7 C. M. McC.Ettlesによる摩擦試験機(1989年)
5.摩耗試験の問題点
5.1 摩耗用標準試験片
5.2 研摩材料の選定
5.3 粘着防止法
5.4 実製品のシミュレーション
6.各種摩耗試験機と試験データ
6.1 回転法による試験
1 ランボーン・改良型ランボーン摩耗試験機(1928年)
2 アクロン摩耗試験機(1940年)
3 H. Westlinningによる高速試験機(1968年)
4 H. A. Geesinkによる摩耗試験機(1958年)
6.2 擦り法による試験
1 ウイリアムス摩耗試験機(1927年)
2 NBS摩耗試験機(1934年)
3 DIN摩耗試験機(1977年)
4 ピコ摩耗試験機(1959年)
5 テーバー摩耗試験機(1928年)
6 A.C.Bassiによる摩耗試験機(1968年)
7 J. H. Thelinによる摩耗試験機(1970年)
8 A. A. Staklisによる摩耗試験機(1972年)
9 T. R. G.Lewisによる摩耗試験機(1947年)
10 E. Southernによる摩耗試験機(1979年)
11 須賀による摩耗試験機(1979年)
6.3 衝撃法による試験
1 R. E. Morrisによるサンドブラスト摩耗試験機(1963年)
7.おわりに
第4章 セラミックスのトライボロジー
1.はじめに
2.セラミックス材料概論
2.1 セラミックスとは何か
1 セラミックスの定義 2 セラミックスの応用分野
3 セラミックスの結晶化学 4 セラミックスの基本物性
2.2 セラミックスの製造技術
1 セラミックス粉末製造技術 2 セラミックス成形技術
3 セラミックス加工技術 4 セラミックス加工技術
5 セラミックス接合技術 6 セラミックス検査技術
3.セラミックスの摩擦・摩耗特性
3.1 セラミックスの変形および破壊力学
1 セラミックスの硬さと機械的特性
2 セラミックス表面近傍の破壊
3.2 セラミックスの摩擦摩耗メカニズム
1 セラミックスの摩擦 2 セラミックスの摩耗
3.3 環境別基礎試験データ
1 室温大気中における基礎試験データ
2 真空中における基礎試験データ
3 高温下における基礎試験データ
4 低温下における基礎試験データ
5 水中における基礎試験データ
6 油中における基礎試験データ
7 特殊環境下における基礎試験データ
4.耐摩耗部品への応用
4.1 すべり軸受
4.2 転がり軸受
4.3 メカニカルシール
4.4 歯車
4.5 自動車用部品
4.6 工具
4.7 生体用部品
5.おわりに
第5章 表面分析のトライボロジーへの応用
1.はじめに
2.材料の表面
2.1 表面と内部
2.2 表面の接触
2.3 雰囲気との相互作用
2.4 摩擦面に現われる変化
3.表面分析法
3.1 表面分析の意義
3.2 トライボロジーに適した表面分析法
3.3 分析上の注意
4.表面分析事例のいろいろ
4.1 超精密加工と表面ひずみ
4.2 摩擦に伴う表面偏析
4.3 焼付き,移着現象
4.4 熱分解生成物とその影響
4.5 摩擦と表面酸化
4.6 腐食環境と摩擦面
5.おわりに
続き省略