出版社内容情報
執筆者(執筆順)
宮前 茂広
石川島播磨重工業(株) 電力事業部 燃焼技術部 部長
中川 二彦
川崎製鉄(株) 水島製鉄所 企画部企画室 主査(課長) 博士(工学)
廣瀬 靖夫
フジサーモテック(株) 取締役技術部長 博士(工学)
長村 彰夫
中外炉工業(株) プラント事業部 ASTプロジェクト プロジェクトマネジャー
中村 泰久
東邦ガス(株) 基盤技術研究部 エネルギー・環境技術グループ総括 副部長 工学博士
毛利 邦彦
電源開発(株) 火力部 調査役
萬代 重実
三菱重工業(株) 技術本部 高砂研究所 主幹研究員 工学博士
今田 守彦
中外炉工業(株) 開発本部 開発部 部長
平野 浩
出光興産(株) 製造部 石油技術センター 燃料油技術課 主任部員
富永 浩章
出光興産(株) 産業エネルギー部石炭研究所 研究主任
武田 信生
京都大学大学院 工学研究科 環境工学専攻 教授 工学博士
梅園 庄治
(株)神戸製鋼所 都市環境カンパニー 環境エンジニアリングセンター 開発部資源循環室 主幹
岡島 重伸
川崎重工業(株) 環境装置事業部 開発部 主事 工学博士
三野 禎男
日立造船(株) 環境・プラント事業本部 システム本部 プロセス機器部 部長代理
鮎川 大祐
(株)タクマ 環境プラント統轄本部 環境計画第2部 副部長
深野 行義
大阪ガス(株) 大阪事業本部 開発営業部 官公庁チーム チーフ 工学博士
定方 正毅
東京大学大学院 工学研究科 化学システム工学専攻 教授 工学博士
原野 安土
群馬大学 工学部 生物化学工学科 講師 博士(工学)
三浦 隆利
東北大学大学院 工学研究科 化学工学専攻 教授 工学博士
青木 秀之
東北大学大学院 工学研究科 化学工学専攻 助教授 工学博士
新井 紀男
名古屋大学 高温エネルギー変換研究センター 教授 工学博士
古畑 朋彦
名古屋大学 高温エネルギー変換研究センター 助手 博士(工学)
鎌田 祐一
名古屋大学 高温エネルギー変換研究センター 非常勤研究員 理学博士
工藤 一彦
北海道大学 大学院工学研究科 機械科学専攻 教授 工学博士
篠田 昌久
名古屋大学 高温エネルギー変換研究センター 非常勤研究員 博士(工学)
八木順一郎
東北大学 素材工学研究所 教授 工学博士
秋山 友宏
大阪府立大学 工学研究科 物質系専攻(化学工学) 助教授 工学博士
加藤 征三
三重大学 工学部 機械工学科 教授 工学博士
大岩 紀生
名古屋工業大学 工学部 機械工学科 教授 工学博士
新美 智秀
名古屋大学大学院 工学研究科 電子機械工学専攻 助教授 工学博士
石野洋二郎
名古屋工業大学 工学部 機械工学科 講師 工学博士
丸山 直樹
三重大学 工学部 機械工学科 助教授 博士(工学)
中村 恒明
東京ガス(株) 研究開発本部 エネルギー環境技術研究所 副部長
福地 健
バブコック日立(株) 呉研究所 火力研究部 研究員 工学博士
(敬称略)
総目次
実践編
第1章 炉の燃焼設計方法
第1節 ボイラのスケールアップ<宮前茂広>
1. ボイラの分類
2. 火炉のスケールアップ
3. 流動層ボイラのスケールアップ
第2節 鉄鋼製造プロセスにおける燃焼装置の設計思想<中川二彦>
1. 鉄鋼製造プロセスにおける加熱の特徴
2. 鉄鋼製造プロセスの燃焼技術
第3節 バーナの設計思想<廣瀬靖夫>
1. バーナ設計の基本的な考え方
2. パラメータ探索の方法
2.1 第一ステップ
2.2 第二ステップ
2.3 第三ステップ
3. バーナ設計パラメータの実際
第4節 築炉設計思想<長村彰夫>
第5節 炉の使用者の視点を考慮した設計<中村泰久>
1. 炉の設計者と使用者
2. 炉の使用者の思い
3. 炉の製作者
4. 加熱炉の種類からみた設計
5. 炉の仕様に求めるもの
6. 設計に必要な考え方
7. コンピュータによる設計
第6節 電力会社における石炭ボイラ用低NOx燃焼器の設計・開発経緯<毛利邦彦>
はじめに
1. 微粉炭の公害物質発生の燃焼過程と燃焼器の設計上の考慮点
2. NOx低減技術の一般的な方法とThermal NOxとFuel NOx
3. 燃焼温度とNOx発生量の関係
4. 石炭火力用バーナの開発の経緯
4.1 (株)日立製作所の場合
4.2 三菱重工業(株)の場合
5. 二段燃焼等による窒素酸化物の低減効果
6. 炉内脱硝技術について
7. 石炭ボイラのNOxの排出量を設計する場合の検討項目
まとめ
第2章 ボイラ火炉の設計
第1節 火炉設計の概要<宮前茂広>
はじめに
1. 火炉の大きさ
2. 火炉断面積負荷の制約と火炉計画への影響
3. バーナの配置計画
第2節 小型ボイラの火炉設計<宮前茂広>
第3節 ストーカ焚きボイラの火炉計画<宮前茂広>
第4節 流動層燃焼ボイラ<宮前茂広>
1. バブリング式流動層燃焼ボイラ
2. 循環流動層燃焼ボイラ
第3章 ガスタービン燃焼器とその設計
第1節 ガスタービンの変遷と燃焼器<萬代重実>
1. 環境、省エネルギーとガスタービン
2. 高温化
3. 低NOx化
4. 燃料多様化
第2節 ガスタービン燃焼器の概要<萬代重実>
1. 設計条件と要求性能
1.1 設計条件
1.1.1 環境条件
1.1.2 運転条件
1.1.3 設計条件
1.2 要求性能
1.2.1 着火性
1.2.2 安定燃焼
1.2.3 燃焼効率
1.2.4 圧力損失
1.2.5 出口温度分布
1.2.6 排気性状
1.2.7 その他
2. 燃焼器形状
3. 燃焼器の特徴
3.1 燃焼負荷率
3.1.1 体積燃焼負荷率
3.1.2 断面燃焼負荷率
3.1.3 空気負荷率
3.2 燃焼領域と機能
第3節 ガスタービン燃焼器の設計<萬代重実>
1. 燃焼器主要寸法
2. 空気配分
2.1 一次燃焼空気
2.2 二次燃焼空気
2.3 希釈空気
2.4 壁面冷却空気
3. 要素設計
3.1 スワーラ
3.2 空気孔
3.3 壁面冷却
3.4 気体燃料ノズル
3.5 液体燃料ノズル
4. CFDの利用
5. 燃料器の設計例
第4節 環境適応型ガスタービン燃焼器<萬代重実>
1. 各種低NOx燃焼法
1.1 水噴射、水蒸気噴射
1.2 希薄拡散燃焼
1.3 希薄予混合燃焼、ハイブリッド燃焼
1.4 触媒燃焼
1.5 二段燃焼・還元燃焼
2. 予混合炎型低NOx燃焼器
2.1 三菱重工業(株)
2.2 GE社
2.3 ABB社
2.4 Siemens社
第4章 加熱方法とその設計
第1節 加熱方法を検討する際の基本的な手順<中川二彦>
はじめに
1. 設計条件
2. 炉の形式
2.1 燃焼熱の伝達方法
2.2 搬送方法
第2節 各種溶解炉<中川二彦>
1. 金属溶解炉
1.1 高炉法
1.2 DIOS法
2. 廃棄物溶融炉
2.1 ストーカ式焼却炉
2.2 低温ガス化燃焼灰溶融方式(直接加熱ガス化型)
2.3 低温ガス化燃焼灰溶融方式(間接加熱ガス化型)
2.4 高温ガス化灰溶融方式
2.5 低温ガス化高温改質回収灰溶融方式(溶融工程一体型)
第3節 蓄熱燃焼を用いた加熱炉<中川二彦>
はじめに
1. 鋼材加熱炉
1.1 従来の鋼材加熱炉
1.2 加熱炉における基本設計の考え方
1.3 蓄熱式バ-ナを用いた加熱炉
1.3.1 バ-ナ配置
1.3.2 蓄熱体
1.3.3 燃焼制御方法
2. 高温気体を用いた噴流加熱炉
第4節 熱処理炉<中川二彦>
はじめに
1. 炉の形式
1.1 バッチ式焼鈍炉
1.2 連続式焼鈍炉
1.2.1 竪型連続焼鈍炉
1.2.2 カテナリー型連続焼鈍炉
2. 熱処理炉における基本設計
3. 炉の加熱方式
3.1 放射伝熱管加熱方式
3.2 直火還元方式
3.2.1 平衡論に基づく方法
3.2.2 還元炎を利用する方法
第5章 工業用バーナの設計
第1節 バーナの基本構造と設計<廣瀬靖夫>
はじめに
1. 燃料の供給口(ノズル)の流量計算
1.1 低圧ガスノズル(ノズルでの圧力20kPa以下の場合)
1.2 中圧ガスノズル(20kPa≦P1<80kPa)
1.3 高圧ガスノズル(P1≧80kPa)
2. 空気導入口の流量計算
2.1 スワーラの流出係数
2.2 バッフルの流出係数
3. 保炎機構
3.1 シールド
3.2 スワーラ
3.3 円筒(半制約空間)
3.4 その他
第2節 バーナ火炎特性の決め方<廣瀬靖夫>
はじめに
1. 空気流速と燃料ガス流速比による火炎特性の変化
2. 空気旋回と火炎特性の変化
3. 燃焼ノズルと火炎特性の変化
第3節 バーナのスケーリング手法<廣瀬靖夫>
はじめに
1. Reynolds数一定のスケーリング
2. 流速一定によるスケーリング
3. 滞留時間一定によるスケーリング
第4節 油の微粒化<廣瀬靖夫>
はじめに
1. 噴霧特性のあらわし方
2. 液体微粒化の方法
第5節 工業用バーナの設計<廣瀬靖夫>
はじめに
1. 産業用ボイラバーナの設計
2. 鉄鋼用バーナの設計
3. セメントキルン用バーナの設計
4. 石油加熱炉用バーナの設計
第6章 炉材と築炉の方法
第1節 耐火物の役割、特徴とその用途<中川二彦>
はじめに
1. 炉において耐火物の果たす役割
2. 各種耐火物の特徴とその用途
2.1 耐火物の基本的な性質
2.2 耐火物の損傷要因
2.3 耐火物の種類とその特徴
1) 耐火レンガ
2) 不定形耐火物
3) 断熱材
2.4 各種耐火物の用途
第2節 実炉における耐火物の使用例
はじめに
1. 金属溶解炉の耐火物
1.1 炉体の耐火物
1.2 炉体の冷却構造
1.3 炉低侵食ラインの設定
1.4 圧入材による高炉熱間補習技術
1.5 出銑樋の耐火物
2. 精錬炉の耐火物
2.1 転炉
2.2 溶鋼用取鍋
3. 加熱炉の耐火物
3.1 一般的な加熱炉
3.2 オールファイバ加熱炉
4. 廃棄物焼却炉の耐火物
4.1 ごみ投入口
4.2 燃焼室
4.3 灰出口部
4.4 二次燃焼室
4.5 ダクト、ガス冷却室
第7章 炉の安全と制御
第1節 燃料の特徴<中村泰久><平野浩><富永浩章><宮前茂広>
1. 気体燃料
1.1 気体燃料の種類
1.2 気体燃料の性質と燃焼
1.2.1 比重
1.2.2 燃焼に必要な空気量
1.2.3 燃焼排ガス量
1.2.4 ガスの発熱量
1.2.5 火炎温度
1.2.6 ウオッベ指数(WI)
1.2.7 燃焼速度指数(CP)
1.3 バーナにおける燃焼
1.3.1 予混合火炎と先混合火炎
1.3.2 火炎の安定性
2. 液体燃料
2.1 灯油
2.2 A重油
2.3 C重油
3. 固体燃料
3.1 種類と特徴
3.2 一般分析
3.3 各種燃焼特性試験
3.4 固体燃料特有の特性試験
第2節 炉の保安<中村泰久><平野浩><富永浩章><宮前茂広>
1. 気体燃料
1.1 安全の三大要素と基本10項目
1.2 燃焼安全装置
1.2.1 燃焼安全制御機器
1) 負荷リレー
2) フレームリレー
3) 安全スイッチ
1.2.2 安全遮断弁
1.3 日本における主な燃焼安全基準・規格
2. 液体燃料
2.1 燃焼安全装置
2.2 燃焼安全装置の基本構成
2.3 火炎検出器の種類
2.4 燃料遮断弁
2.5 シーケンス制御装置
3. 固体燃料
3.1 炉前の管理
3.2 炉本体の保安管理
3.2.1 微粉炭機(ミル)の保安管理
3.2.2 ボイラ火炉の保安管理
1) 空気流量極低
2) 炉内ドラフト異常高または異常低
3) 全押込ファン停止
4) 全誘引ファン停止
5) 燃焼中バーナの全火炎喪失
6) 燃焼中バーナ多数の火炎喪失で、プラントが危険な状態に陥る可能性が高い場合
第3節 基本的な制御<中村泰久><富永浩章><宮前茂広>
1. 温度制御
1.1 ON-OFF制御
1.2 時間比例制御
1.3 PID制御
2. 空燃比制御
2.1 ブンゼンバーナ(インジェクター)方式
2.2 ゼロガバナー方式
2.3 均圧弁方式
2.4 コントロール弁リンケージ方式
3. 環境性能に関わる制御
3.1 低NOxバーナ
3.2 二段燃焼技術
3.3 排ガス再循環技術
4. 安全に関わる制御
4.1 保安機器
4.2 燃焼制御と保安インターロックシステム
4.3 バーナ制御装置(BMS,Burner Management System)
4.3.1 BMSの制御機能
1) 点火・消火機能
2) 共通保護機能
?@ 火炉パージ機能
?A リークチェック機能
?B バーナ自動パージ
?C 点火許可条件確認
?D バーナ火炎監視
a) 個別バーナトリップ
b) 全火炎喪失
c) バーナ多数失火
第8章 環境保全型燃焼方法
<8章監修 武田信夫>
第1節 フロンの分解燃焼<梅園庄治>
1. フロンの分類と性質
2. フロン分解法の紹介
3. 分解燃焼例の紹介
3.1 ロータリーキルン法
3.2 液中燃焼法
第2節 ダイオキシンの分解燃焼<岡島重伸>
はじめに
1. ダイオキシンとは
2. ごみ焼却処理プロセスにおけるダイオキシン類の生成
2.1 一次生成
2.2 二次生成
3. ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン
第3節 プラスチックの分解燃焼<三野禎男>
1. プラスチック廃棄物の特性
1.1 プラスチック廃棄物の種類
1.2 プラスチック廃棄物の熱分解燃焼特性
2. プラスチックの分解燃焼
2.1 キルンによる燃焼
2.1.1 積極燃焼実験
2.1.2 ガス化燃焼(緩慢燃焼)実験
2.2 熱分解流動床による燃焼
2.3 プラスチックフラフの燃焼
3. プラスチックの分解燃焼における二次公害対策
第4節 自動車などの複合材の分解燃焼<鮎川大祐>
1. 廃自動車の処理
2. 熱分解ガス化溶融発電プラントの設計
3. プラント運転
4. リサイクル
まとめ
第5節 コージェネレーションにおける燃焼 <深野行義>
1. コージェネレーション
2. ガスエンジンにおける燃焼
2.1 点火時期の影響
2.2 空燃比の影響
2.3 圧縮比の影響
3. ガスタービンにおける燃焼
第9章 燃料の燃焼
第1節 熱力学と化学平衡<定方正毅><原野安士>
はじめに
1. 燃焼の熱力学
2. 燃焼と化学平衡
3. 化学平衡の温度依存性
4. 燃焼ガスの化学平衡と断熱平衡燃焼ガス温度
第2節 燃焼と反応速度論<定方正毅><原野安士>
1. 素反応と反応速度
2. 詳細化学反応機構モデル(Full kinetics)
3. 感度解析
4. 準定常近似と部分平衡
第3節 気体の燃焼<定方正毅><原野安士>
1. 気体燃料
2. 気体の燃焼機構
2.1 連鎖反応
2.2 水素-酸素の燃焼機構
3. 一酸化炭素の燃焼機構
4. 炭化水素の燃焼機構
4.1 メタン-酸素燃焼の反応機構
4.2 エチレンとアセチレンの酸化機構
4.3 アルカンの酸化機構
4.4 芳香族炭化水素の酸化機構
第4節 液体の燃焼<定方正毅><原野安士>
1. 液体燃料
2. 液体燃料の燃焼
2.1 液滴の予熱期間
2.2 液滴燃料の蒸発期間
2.3 着火遅れ
2.4 定常燃焼期間
第5節 固体の燃焼<定方正毅><原野安士>
1. 固体燃料
2. 固体の燃焼
2.1 固体燃焼の燃焼速度
2.2 炭素粒子の燃焼
2.3 Char粒子の燃焼
2.4 石炭の燃焼
第6節 燃焼計算<定方正毅><原野安士>
はじめに
1. 理論空気量
2. 理論燃焼ガス量
3. 空気比
4. 燃焼ガス組成
5. 理論燃焼温度
第10章 大気汚染物質の生成
第1節 窒素酸化物の生成<定方正毅><原野安士>
はじめに
1. NOの生成機構
1.1 Thermal NO
1.2 Prompt NO
1.3 Fuel NO
2. NO2の生成機構
3. N2Oの生成機構
第2節 硫黄化合物の生成<定方正毅><原野安士>
1. 燃料中の硫黄化合物
2. 硫黄化合物の生成機構
2.1 硫黄燃料の酸化機構
2.1.1 H2S
2.1.2 COSとC2S
2.2 有機硫黄化合物の酸化機構
2.3 重油や石炭からの硫黄化合物の生成機構
2.4 黄鉄鉱(FeS2)の反応
2.5 SO3の生成
第3節 塩素化合物の生成<定方正毅><原野安士>
1. 塩化水素の生成機構
2. ダイオキシン類の性質
3. ダイオキシン類の特性
4. ダイオキシン類の生成機構
4.1 前駆物質からの有機化学反応による合成
4.2 de novo合成
4.3 燃焼でのダイオキシン類の発生
第4節 炭素質粒子状物質の生成<定方正毅><原野安士>
1. 炭素質粒子状物質の性質
2. すすの生成傾向
3. 燃料の熱分解
4. すすの核生成
4.1 すす前駆体の熱力学的安定性
4.2 ベンゼンの生成機構
4.3 Frenklachらによるすすの生成機構
4.4 炭素クラスター経由のすすの機構
第11章 炉内におけるガス流れ
第1節 炉におけるガス流れ
第2節 層流火炎と乱流火炎時のガス流れ
第3節 炉内の浮力
第4節 流動抵抗
第5節 煙突の設計法
第12章 炉内の伝熱
第1節 炉内伝熱の概念
第2節 固体のふく射
第3節 ガスふく射
第4節 輝炎とすすからのふく射
第5節 炉内ふく射伝熱
第6節 炉内伝導伝熱
第7節 炉内対流伝熱
第13章 エネルギー利用効率
第1節 エクセルギー解析
第2節 流通プロセスの物質収支
第3節 修正エンタルピー収支
第4節 輝炎とすすからのふく射
第14章 炉における測定法
第1節 制御のための物理量計測法
第2節 燃焼性状の計測法と可視化技術
第15章 シミュレーションソフト
第1節 バーナ火炎シミュレーション
第2節 工業炉設計支援用前処理ソフト
資料編
索引
-
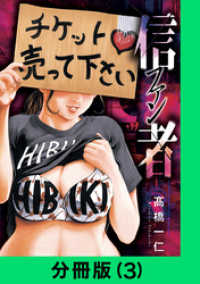
- 電子書籍
- 信者~ファン【分冊版(3)】 LINE…
-
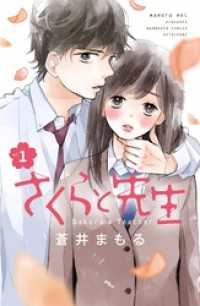
- 電子書籍
- さくらと先生 分冊版(1)






