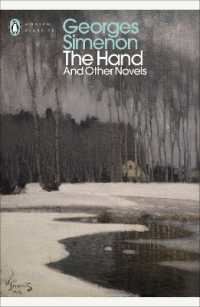内容説明
二〇二一年三月に刊行された『フーコー研究』(岩波書店)をめぐって、同年三月末に京都大学人文科学研究所主催で開催されたシンポジウム「狂い咲く、フーコー」の四時間半にわたる議論に、各発言者が加筆。四〇〇名にも及ぶ聴講者を集めたオンライン・シンポジウムの全記録。二〇世紀フランス現代思想の代表的知識人ミシェル・フーコー。その新たな研究が日本発ではじまっている。京都大学人文科学研究所が二〇一七年より三年間にわたって活動した研究会の記録を基にして、『フーコー研究』が刊行された。その内容・テーマを各執筆者がダイジェストに紹介し、議論する。最新のフーコー研究への誘いの書。総勢三二名の執筆者は、専門領域も異なり、それぞれの分野から、精緻なフーコー研究がなされている。フーコー研究者のみならず、初学者が紐解ける“入門の書”。
目次
第1部 フーコーの全体像・読む「方法」・新自由主義(フーコーの巨大な重力;真理と虚偽、宗教と無神論、理性と非理性、文化と野蛮;フーコー像をどう捉えるか;フーコーを読む「方法」;フーコーと新自由主義 ほか)
第2部 パレーシア・生と死と文学・主体/精神分析(「なんでも語ること/忌憚なく語ること」から「真理を語ること」へ;パレーシアの核心にあるもの;「自身の理性を用いる勇気」と「真理(へ)の勇気」
主体の問題と精神分析
主体の生と死をめぐって ほか)
-

- 電子書籍
- ソード・ワールド2.5サプリメント ヴ…