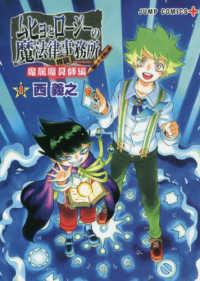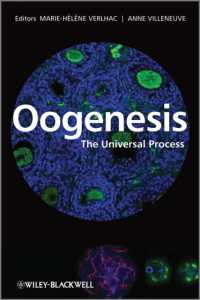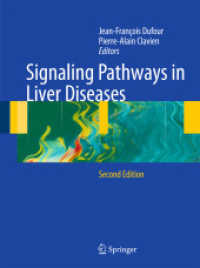内容説明
貧困家庭の子どもから見える、家族、学校、友人関係、そして自分の将来。「流行についていけない。」「放課後友だちと遊ぶお金がない。」…現代の消費社会のなかで、いじめや排除と隣り合わせに生きる子どもの貧困経験を、子どもに直接インタビューすることで得られた生の声をとおして浮き彫りにする。
目次
第1章 挑戦的課題としての「子どもの貧困」―子どもを中心に据えたアプローチ
第2章 子ども期の貧困について、私たちはなにを知っているのか
第3章 経済的・物質的資源を子どもたちはどう確保しているか
第4章 「仲間に溶け込むこと」と「仲間と参加すること」―社会関係と社会統合
第5章 家庭生活と内省
第6章 学校についての体験と認識―イギリス世帯パネル若者調査(BHPYS)データの分析
第7章 子ども期の貧困と社会的排除―子どもたちの視点を組み込んで
付録 第七回イギリス世帯パネル若者調査(BHPYS)について
著者等紹介
リッジ,テス[リッジ,テス][Ridge,Tess]
イギリス・バース大学の社会・政策科学部上級講師
中村好孝[ナカムラヨシタカ]
滋賀県立大学人間文化学部助教(社会学専攻)
松田洋介[マツダヨウスケ]
金沢大学人間社会学域・学校教育学類准教授(教育社会学専攻)
渡辺雅男[ワタナベマサオ]
一橋大学大学院社会学研究科教授、社会学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
す
1
貧困に苦しむ子どもの生の声を多く取り上げていた。彼らの多くが、自立を望んでいたり、親に多くを期待していないことが印象的であった。かといって、親を嫌うわけではなく、親を配慮する発言も多く見られて、自分の現状について深く考えていることが分かった。制度的な改革が必要であるのは間違いないが、まずはやれること(私服の日の廃止や無料給食のICカード制など)からやっていくべきで、それだけでも充分に子どもの自己肯定感や社会とのつながりを持たせ、疎外感の軽減が可能であると思う。2014/02/07
モジャ
0
イギリスにおける子どもの貧困、そして社会的排除の影響がどうなっているのかを、実際に子ども達へのインタビューなども行って研究をした一冊です。これまでの貧困の議論において子どもが置き去りにされてきた。子どもが中心となるのではなく、「家族」や「被保護者」として捉えられ、必ずしも効果的な対策がとられてこなかった。それは研究も同様であり、子どもに「関する」研究はあっても、子どもと「ともに」、子どもの「ために」行う研究はなかった。それをこの一冊では試みている。2011/04/03
ぼーん
0
イギリスの子どもの貧困を扱った本。本書は中ではchildfood povertyの訳語を使っているけれども、その内容は日本語版のタイトルの意味通り、child povertyで良いと思う。貧困状態にある子どもの実態を調査によって把握している書。
-
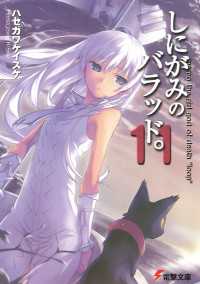
- 電子書籍
- しにがみのバラッド。(11) 電撃文庫